誰かに呼ばれているような気がした。
「ヒビ、ヒビ。こっちおいで、かえっておいで」
優しく手をさし伸ばす。誰だろうか?たった一人の肉親の母親か、それとも幼馴染のあの子だろうか。
――現実は、どちらも違った。
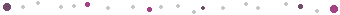
いささか頭痛がするが、回りを見渡す。そこには黒板もあり、机もあり、荒れた古臭いフローリングの床が広がる。あぁ、教室で寝ちゃったのかな。一瞬そう思った。
そこで俺―新宮響(男子9番)―は机に突っ伏している自分のクラスメートを見回してみる。珍しい、どうして皆寝てるんだろう。また、当然のように夏葉翔悟(担任)はいない。こんな普通の状況をなぜか不審に思った俺は、斜め後ろの席に座っている幼馴染の蓮川司(女子9番)をゆすって起こした。彼女のその茶色の髪の毛がさらさらと揺れ落ちる。
「司、司。起きろよ」
彼女はうぅ……と不機嫌そうに声を絞り出す。やがてゆっくりと目があくと、うつろな視線でこちらを見た。
「響……?」目をこすってその長い髪を丁寧に整える。
「俺たち……何やってたんだっけ……」
記憶の端をたどるが、まるで誰かが斧で断絶したようにその向こうはさっぱりわからない。ズキン、とまた頭が痛み出した。
「ってぇ……」
「大丈夫?」
すかさず司が席を立ち、俺の席の方へと近づいてきた。その心がけはとてもとてもありがたかったが、そのおかげで俺はある異変に気づいてしまった。
「司……お前……その首につけてるの……」
「首?」
怪訝そうにこちらを見ながら、半信半疑で首をさする。そして次の瞬間、彼女の表情が変わった。
「……なに、これ……」
多分俺は、その問いに答えることは出来ないだろう。
「……ひー君?」
突然、この部屋の一番前の席から声がした。俺のことをひー君と呼ぶのは、妙なあだ名をつけたがる男子学級委員の郡司崇弘(男子6番)しかいない。彼も俺たちと同様に眠い目をこすった。そのとき妙に違和感が感じられなかったのが、それが彼のいつもの行動だからだろう。
「タカ! よかった……なぁ、俺達どうなっちまってるんだ?」
「わ……わかんない。けど……」
一瞬言葉をためらって崇弘は後ろの席の親友・藤原優真(男子11番)をたたき起こす。だが彼はよほど心地よい眠りの真っ最中なのか、寝言を言いながら顔だけ寝返りを打つ。
「けど、すごく、いやな予感がするんだ」
珍しく寝癖の立っていない髪の毛のほうが、よほど嫌な予感を示唆しているよ、と危なく場違いな突込みをしそうになった俺だが、その言葉を飲み込み、ただあやふやにうなずくだけだった。
「うっ……」
郡司の2つ右隣の席、羽田拓海(男子12番)が顔を起こした。一瞬ボーっとした視線を黒板に向けたが、覚醒するように目を見開いてすぐさま周りを見渡し、俺達を見つけるや否や「どうしたんだ、どうなってるんだ」と哀願するように視線を送っている。そういった視線を送っているということは、何も言わなくても解る。彼はいつも1人で突っ走っていて、尻拭いは全部他人に任せるのだから、この状況での思想は、成り行きから行ってもそんなところだろう。
「俺達……音楽室にいたんじゃ……」
身体をひねらせて隣の席の神谷真尋(女子4番)を起こす。普通なら真っ先にすぐ後ろの同姓、森井大輔(16番)を起こすはずじゃぁないのかな、とは思ったが、まぁそこは黙認しておこう。
だが大輔も羽田に起こされる前にちょっとした騒ぎに気付き(さすがに敏感なところは変わらないようだ)、ゆっくりと身体を起こした。
「……響? ……タカ……」
大輔も俺と同じく頭痛がするのか、頭を抱えたまま薄ぶちのメガネを上げる。そしてその特徴ある長い前髪を綺麗に振り払った。ああ、ああやってクールに髪の毛を振り払っても、美しいと思える男に俺はなりたかったのかもしれない。
「大輔! よかった、お前も周りの奴起こしてくれよ!」
「……何があったんだ……ここは……」あたりを不思議そうに見渡しながら、後ろの席の相澤圭祐(男子1番)をたたき起こす。彼は藤原優真同様にむにゃむにゃと寝言交じりに目を細めていたが、すぐに大輔に頬をつねられると、覚醒したように目をぱちくりとさせた。
俺も崇弘も羽田も大輔も、思っていることは一緒だった。ここはどこだ、どうして俺たちはここにいるんだ。
「モリィ、サワスケ。梅雨子とかジョウさん起こして!」
半ば声が裏返りながら、崇弘は言う。ちなみにモリィというのが森井大輔、サワスケは相澤圭祐、梅雨子は高木時雨(女子6番)、ジョウさんは上条達也(男子4番)のことだ。ぱっと聞いただけでは誰だかわからない、それが郡司崇弘のつけるあだ名なのだ。
「響……」
周りの工藤依月(男子5番)や土屋若菜(女子7番)、吉沢春彦(男子17番)などを起こしている途中、後ろから袖口を引かれた。振り向けばそこには司が心配そうな顔で見上げている。彼女は何も言わずに無言で服をぎゅっとつかんでいた。言いたいことは解る。
「大丈夫、俺がいるだろ?」自然と、笑った。
「ね……ねぇ皆ぁ……」
この部屋でいう、ちょうど中央部分の席に座っていた諸星七海(女子14番)が、顔から血の気を引いた状態で辺りを見回し、そして親友で幼馴染の遠藤雅美(女子2番)の席まで近寄り、その腕にしがみついた。
「どうして……? 雅美も、イサ君も藤原君もタカちゃんも、司ちゃんも若菜ちゃんも……、綾香ちゃんも佑恵ちゃんも、皆どうして……」
確かに彼女の声は、蚊の羽音並に小さなものであったが、真夏の夜同様、辺りが静まっていると大きく聞こえるものだ。誰かののどが動くのが解る。その続きに対し、クラスの全員が起き上がり視線を集中させた。
「どうしてその銀色の首輪つけてるの……?」
諸星の大きな瞳からあふれんばかりに涙が浮かんだ。初めて気がついた人も居たのか、すぐに自分の首を触り、あれやこれやと思い思いに叫びだす。
「何だよこれ!」
牧野尚喜(男子13番)がいかにも心の底から驚いた、というような叫び声をあげた。既に彼の目には涙すら浮かんでいる。そりゃぁ泣きたくなる気持ちもわかるよ。いきなり眠らされて銀色の首輪だぜ?ドッキリにも程があるって話だ……。
「おいおいー、これじゃぁ俺のナイススタイルがマイナスになっちまうぜー」
ギクシャクした笑いと共に親友であり部活仲間の市村翼(男子3番)が皆の暗い空気を吹き飛ばそうと、ちょっとしたジョークを言う。だが今この状況では逆効果なのか、すぐにしんとした雰囲気が流れる。
遠藤雅美の前の席、女子学級委員の望月千鶴(女子13番)は、一回だけめがねの中央部分を押さえると、郡司のほうを振り向いた。
「タカ……」何かを哀願するような目だ。
郡司がその意思を読み取り、何かを口にしようとしたそのとき、突然部屋の入り口のドアがガラッという音を立ててあいた。
「はーい、みんな、こんにちわっすー! 出来れば今起きてない人を起こしてほしいっすー」
真っ赤なパーカーを羽織り、胸元に大量のプリントを抱えてこの部屋に入ってきたのは、やけに若い、およそ20代前半の小柄な男だ。だが20代前半なんて一瞬でも思った俺がバカだった、彼はどう見ても俺らと同じ、もしくはすこし上くらいにしか見えない。大量の紙を教壇らしい机の上にどさっと乗せると、手を二、三度はたいてから、なにやら黒板に白いチョークでガリガリと書き始めた。
何が起こっているのかまったくわからない状況に陥っていた。確かに「まさか」、「もしや」、という不安はあった。だがそれは、きわめて可能性の低いものだろう?
首輪、知らない場所、知らない男。
疑うだけの要素はしっかりと揃っているではないか。
赤パーカー男はどうやら黒板の文字を書き終えたようで、くるりとこちらを振り向き、その長身で隠されていた文字が、全体に見えるように身体を移動させた。
「えーっと、君たちは、極めてまれなラッキーボーイズガールズっす!」
にっこりと笑うと、持っていたチョークで黒板に書かれていた文字を指す。
何の変哲もない、大人の書くような文字。いってしまえば普通よりはうまいほうだ。だがその筆記で書かれた文字というものに、それもたかが文字というものにだ。その文字を見て血の気が引き、今にも貧血で気絶しそうな体験を覚えたことはない。
第六十八番プログラム:1998年:第50号
「千葉県高原市立第五中学校3年A組の生徒さんたちは、プログラムに選ばれたっす!」
静寂が、一気に冷やされた気がした。
Next / Back / Top
