もう、今となってしまえば遠い昔の体験談のように思える。いや、体験したかどうかも疑わしい夢のように、実感がない。
――七海ちゃぁん、待ってよぉ、若菜を置いていかないでよぉ〜
だいいち今こうして生きていることが奇跡に近い。もうそろそろ死んでいいころだと自分でも思うのに、いまだ生きているこの生命の不思議。
――若菜を独りぼっちにしないでよぅ〜
だけど頭の中は、身体より先に死んでしまいそうだった。
ずっと、ずっと一人で苦しんでいた――。
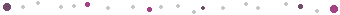
諸星七海(女子14番)は、ただ自身の脳裏を行ったり来たりする土屋若菜(女子7番)の助けを求める声だけにさいなまれ続けた。諸星がずっと隠れていたところ、運悪く冷静を失った土屋と遭遇したのはもう10時間ほど前になる。事情はよく分からないがおそらく誰かに裏切られたのだろう、神谷真尋(女子4番)や蓮川司(女子9番)の名前を連呼しては「若菜がやったんじゃないよ」と涙を流しながら訴えかけてきた。
もともと土屋はその男好きでかなりのぶりっ子であることから、高原第五中の3学年に有名な五大性格ブスの一員である。諸星はもとよりクラスメートからもあまりよく思われていなかった。だから裏切りにあったとしてもおかしくはない。
が、諸星にとっての問題はここからだった。狂った土屋から逃げようとしたところ、左腹部に被弾してしまった。助けを求めていた彼女は、どんな手を使ってでも諸星にそばに居て欲しかったのだろう。それに当時の土屋は自我を失ってやっていい事と悪いことの区別すらつかないただの自己中心的になっていた。だから発砲することが、最悪なことも理解できなかったと言うことになる。
必死の思いで激痛の走る左腹部を庇いながらD−09エリアにたたずんでいた。ここは竹林のようなブッシュはまったく無く、ただ広がる広い田んぼと畑、それから農家らしき立派な家が点在している場所だった。周りの障壁はまったくないので、これでは敵に見つけられたとき狙撃されそのまま死んでもまったくおかしくはない。もし、自分に支給されたのがこんなクマのぬいぐるみではなく、もっと別の使える武器だったなら、話はまた変わっていただろう。なのにどうして諸星はこの場所から動かなかったのか――それは、もう既に彼女の身体は、脳から発せられる信号を受け付けるだけの力がほとんどないからだ。被弾し、ぽっかりあいた左脇腹の銃創からは血が止まらなくなって久しい。全身の血液がすべてその穴から流れ出てしまったと言っても過言ではないほど、諸星は失血していた。これほど失血しておきながらよくもまぁ半日ほど生きてこれたな、と自称気味に彼女は細く笑う。
広大に広がる畑地域は、先にもあるように障壁がなく、敵との対峙は極めて死に近いことを意味しているので、この場所に来ようと思っている人間はかれこれ夜になるまで居なかった。したがってほとんど逃げるために動く機会が無かったので、余計に血を必要とはしなかった。それでも失血多量で諸星は顔を真っ青にし、頬もこけた表情でもう一度口元を笑みの形につくろった。
――七海ちゃぁん、若菜もうやだよぉ! 恐いよぅ、家に帰りたいの……
いつでも土屋若菜の言葉が頭を離れたときはない。先ほど流れた放送では彼女の死が伝えられ驚愕していたところなのだ。幻聴はさらに音量を増し、諸星に深く鋭く突き刺さり、挙句の果てには内部のものを抉り取られたような思いをした。
どうして、どうして生きているんだろう――諸星は元々細い目をぎゅっと瞑った。
自分は若菜さんを見殺しにした。もしあそこで私が若菜さんをうっとうしがらないで、ちゃんと優しくしてあげられたなら、きっと私は今頃こんなただ死を待つような感じにならなかっただろうし、それに若菜さんだって死なずにすんだかもしれない。ごめんね、ごめんね若菜さん。私がいけないんだよね……若菜さん、ただ怖かっただけなんだよね、私だってそうだけど……。私が馬鹿だったよ、ごめん。甘えないでなんてきついこと言ってごめんなさい。どうか許して、だからもう私の頭からでて言って、これ以上私を苦しめないで。
せめて、安らかに死なせてよ。
諸星は田んぼを区切る農道の横に一本だけはえている背の低い広葉樹の木の幹に体を預けながら、深く深くため息をついた。
もう自分は生きるべき人間ではないと思った。人を見殺しまで、ましてやこんな死にぞこないになってまでもなお、どこに生きる理由があると言うのだろうか。幼馴染である遠藤雅美(女子2番)は、まだ放送で名を呼ばれていないにしろ、もう自分のことなど忘れているのだろう、と彼女は考えていた。もともとクラスでもおとなしい部類で、学校を休んだとしても下校時まで気付かれないような人間だったし、例え幼馴染といえど不良と呼ばれ、ピアス茶髪はお手の物、態度まで勝気な遠藤の眼中に入っていなかったのだろう。そう諦めることでしか、この現実を受け入れることは出来なかった。
誰にも求められず、誰も求めず、一人で死んでいくこの寂しさ。体がまだ動いていたときにはそんな悲しさに胸が締め付けられて、早く遠藤に会いに来て欲しいとさえ思ったが、もう死が目前となっている今は、そんなこと別にどうだってよくなっていた。
――雅美は私のことなんて工藤君の次。そんなこと、わかってるけどね。
遠藤が一番好きだったのは、秀才の名をほしいがままにしているくせに授業にまともに出ず屋上で一日のほとんどをすごしていた工藤依月(男子5番)。彼もまた名前を呼ばれていないから、おそらく探しに行ったんだろうと諸星は考えていた。
もう、いい。どうせ私は死ぬんだから、もういいんだ。
また諸星は引きつった笑いを見せ、真夜中といえど少し明るい空を見上げてため息をついた。今にも雨が零れ落ちそうなくらい膨れ上がった雲が、都会のライトを反射して明るく光っている。かすかに残った感覚のうちのひとつの嗅覚を駆使してにおいをかぐと、ほんのりとあの都会の雨特有のにおいがしてくる。ああ、朝ぐらいには雨がざっと降ってくるだろうなぁ……と考えながら諸星は瞳を閉じた。
一人なら、なれている。一人っ子として育った所為か、友達がいなくても1人で遊ぶことを覚えた。むやみに広く友達を作ることはあまりしてこなかったため、クラスでも目立った子ではなかった、と言うことに結びつくのだが、それは彼女自身が悪いわけではなく、彼女の考え方が引き起こしたことであった。
独りだって大丈夫だよ、私、ずっと1人だったもん。
クラスの端っこからわいわい騒ぐ主流はグループを見てはため息をついていた。引っ込み思案で、気が弱くて、そのくせ自分の中では友達なんてたくさん必要ないと粋がっていた自分がそこにいた。憧れていたのは男子だ。友達と隔たりなく(まぁ、多少はあったにしろ女子のグループ形成よりはまだマシだ)付き合えると言う関係が羨ましかった。女子ではよく柳葉月(女子15番)や土屋若菜、神谷真尋(女子4番)、野口潤子(女子8番)などが声をかけてくれたが、その行為を無碍にしたのは誰でもない、自分自身だ。もう、彼女達も死んでしまった。頭の片隅で思い出した名簿の黒く塗られた欄に彼女達の名前はある。先ほど放送された分はもう体力がなくて記入することは出来なかったけど、禁止エリアもそれほど重要ではなかった。長く生きられない自分には、だが。
不思議だ、どうして死ぬ間際になって今更感傷に浸ってるんだろう、と自分が嫌になったが、諸星はすぐにその考えを振り払った。だがすぐに思い出したくないものが頭をよぎる。もう何回このことについて考えたことだろうか――卒業式間近と言うことで、クラス全員にひとつずつ配られた色紙。自分以外のクラスメートがそこになにかを書いてくれると言うものなのだが、半分も埋まらなかった諸星の色紙――数は数えていないが、もう長い間こうしてくだらないことが繰り返し反芻されていたのだ、軽く100回は越えているだろう。はじめは諸星を容赦なく痛めつけていたその色紙の苦い思い出だが、もう回を重ねたことにより他人事にさえ思われていた。
思い出したくないことばかり思い出して、それでいて何回も繰り出してくる腐った脳に乾杯。
――七海ちゃぁん、待ってよぉ、若菜を置いていかないでよぉ〜
まただ。色紙の残像が消え、土屋若菜の幻聴が蘇ってくる。いい加減その声には飽き飽きだ。そう、もう何度同じことを考え、同じように苦しめられ、同じようにそんな自分に飽き飽きしているのだろう。もうそろそろ断ち切ってもいいような悪循環に諸星は嫌々していたが、それを己の手で断ち切ることすら出来なかった。
「……雅美」
自分の手で区切りを付けられないのなら、いっそ他人に救いをもめるしかなかった。誰も自分を助けてくれる人はいない。今も前もずっと、そう割り振って理解してきたはずなのに、言葉ばかりは弱気になり、届かない助けを求める。
「まさ……み」
弱い、情けない。死んだ人間に振り回されて命かながら生と死の境界線を歩いている自分が醜かった。そんな自分が大嫌いで、いっそ死んでしまっても、誰も悲しまないだろう。
七海!!
――土屋に撃たれた際に聞こえた遠藤の助けを請うような叫び声がまた聞こえてきた。どうせ今度も幻聴なのだろうと諸星はそれほど気にしなかったが、どんどん大きくなるその声にふと疑問を抱いた。
私を呼ぶのは、だれ?
「やっと見つけた……!」
頬が少し揺れる。痛みなんて感じていなかった。――私を呼ぶのは、誰?
「大丈夫か七海! 俺だよ、俺だ!」
ななみ?私の名前?
頭の中では色々気難しいことばかり考えていたのに、いざ簡単な単語を耳元で言われると理解しにくい。頭はもう動かず、頬を叩かれる感覚が彼女を支配していた。
「まさ……み、な……の?」
久々に開いた唇の奥、口腔はすっかり乾ききっていたので、諸星は必死につばを飲み込み、目を開けた。今まで暗かったはずの視界がほんの少しだけ暗くなって、茶髪が目立つ遠藤雅美の姿を薄ぼんやりと確認できた。遠藤は両耳にヘッドフォンのようなものをつけていたが、それをはずして首にかける。しかし諸星の視界はまるでサングラスをかけているようで決して良好とはいえない。それはつまり、もう彼女の身体は視覚にも限界が来ているということだった。今では、遠藤が殺した服部綾香(女子10番)や土屋若菜の返り血で赤黒く染まった白いブレザーの色も分からない。
「誰だよ、誰にやられたんだよ!?」
視界が途切れた。もしかしたら無意識に目を閉じてしまったのかもしれない。死と言う自然の摂理に身を任したまま、諸星は耳からは言ってくる遠藤の怒声を聞き取った。しかし彼女には遠藤が何を言っているかすら分からない。ただただ、幼馴染が目の前にいると言う情報しか処理できなかった彼女は、「あい……に、来て、くれ……た、の?」と途切れ途切れに辻褄をあわさず聞く事しかできなかった。
遠藤はもう諸星の様子を見てすべてを悟ったようだ。あえて自分の質問を強制せずに、
「当たり前だろ!」と答えた。
諸星は精一杯の力を込めて、細い目をいっそう細める。その糸目の端からは涙が滴り落ち、彼女の背中を抑えて上半身をあげている遠藤の腕に落ちた。
今の諸星には、たとえ遠藤が分校で青沼聖に宣言したように、犬猿の仲だった性格ブスの一人である服部綾香を殺したとしても、そんなことはどうでもよかった。目の前にいる人間が人殺しだとしても、諸星のたった一人の幼馴染であることには間違いはない。諸星の、たった一人のよりどころであることにも。
「く……どう、くんは?」
最後の力を振り絞って諸星はそう質問する。
「アイツはいい! あんな奴より、俺はずっと、ずっと七海のほうを探してたんだから……な?」
ずっと自分は工藤依月の次だ、と思っていた諸星の考えが翻された。不意に自分が少しでも他人に愛されていたことに気付く。
――よかった、私、雅美に認められてたんだね……?
言葉にすることは出来なかったが、頭の中では喜びが広がっていた。今まで彼女を苦しめていた幻聴やくだらない思い出の濃い霧が一気にはれ、清々しささえ感じられる。
しかし、次の瞬間、その清々しさは血の色に染められることとなった。
ダダダダダッ……
古ぼけたタイプライターと言うには、まだ『壊れかけた』と言う形容詞が足りず、コンクリートを平らにするあの現場道具と言うにはすこし音が小さい――急にそんな連続音が聞こえた。
遠藤の背中の方角からは火花のような閃光がついたり消えたりして、3秒ほどあとにはすぐに消えた。その後の変化といえば、遠藤と諸星の体中に細かな穴が空き、そこから血が噴水のごとく飛び出してきた、と言うことだろうか……。
残り12人
Next / Back / Top
