いつだって、俺にとってのあなたは、大きな背中をした人だ。
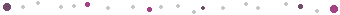
名前に似合わず真っ赤なパーカーを羽織った青沼聖(副担当教官)は、先刻からせわしく分校の一角のコンピュータールームを動き回っていた。元々年齢のわりには小柄なせいか、余計小動物が動き回っているようで、パソコンや生徒監視用の大画面ディスプレイと睨めっこしていた兵士達にはたまらなく目障りなものだったろう。それでも青沼は周りの目を気にせずに必死になって動き続ける。だが最終的には痺れを切らし、「スミマセン!夏葉先生どこいったか知らないっすか?!」と焦りに近い叫び声をあげた。
時は午前5時半。6時の定時放送まであと30分を切ったところだった。いつもならこの頃からちゃんと放送に対しての準備を済ませようとするのだが、肝心の夏葉翔悟(担当教官)の姿がない。元々面倒くさがり屋で、仕事をサボることなど当たり前のように振舞う人間だったから、どこかに隠れているのだろうと踏んで青沼は探していたのだが、どこを探してもその姿は見つからない。結局青沼のため息が、パソコンのファンの音に混じる結果となった。
「夏葉担当教官なら、先ほど上の階の方に行きましたが」
一人の兵士が声を上げる。青沼はすぐにそっちのほうを振り返ると「あーもう、またサボって……」とつぶやくとすぐに「ありがとうございます! じゃ、俺ちょっと夏葉先生引き戻してくるんで、その間よろしく頼むっす!」と言いながらパソコンルームをとびだした。
上の階といえばすぐそこに階段があり、それを駆け上ればいい。木製でぎしぎし鳴る音を気にしながらも、青沼は小走りに急いだ。
青沼は走りながら頭を掻いた。彼の『そう言う性格』を知っていたにもかかわらず逃走されるとは、あの部屋に置かれている人間への配慮の眼もまだ届いていなかった証拠だ。それとも自分は夏葉先生なら大丈夫、とでも思ってたのか?自問してみるが答えは焦りにかき消された。夏葉が部屋から消えたことは放送の時間が近いと言うことを抜かせばそれほど重要なことではないのだが、何よりも今、ようやくプログラムにおけるお楽しみの時間が訪れていて青沼の気分も高揚していたと言うのに、それをめちゃくちゃにされたのに立腹したのだ。
「なーつはせーんせー!!」
階段をあがってすぐの部屋の扉を開ける。面倒くさがり屋でサボることに関しては周到な準備を重ねるくせに、今回はやけにあっさり捕まった夏葉はその部屋の奥に置かれているソファーに仰向けに寝転がっていた。頭の後ろで腕を組み枕代わりにして、顔の上には生徒資料の紙束が乗せられていた。
「夏葉センセー、そろそろ放送の時間っすよ?」
少しだけ息を切らしながら青沼がそのソファーに近寄る。しかし夏葉はうんともすんとも言わなかった。本当に熟睡しているのだろうか?青沼はふと先ほど見た時計の針を思い出す。午前5時半、普通の人間なら、寝ていてもおかしくはない。だがそれはあくまでも普通の人ならば、と言う条件だ。プログラム担当官に休憩はない。
「夏葉先生」
すぐそばまで寄ってぴたりと止まる。あえて揺らし起こすことはしなかった。彼は横たわる夏葉を見下しながら、ボソリと「夏葉サン」と言う。
数秒たっただろうか、夏葉の手が動き、顔の上に置いておいた資料を剥がす行動をしながら「なんだよ気持ちワリィな。青沼がサン付けなんてよ」と疑いの目を向けながら目を開けた。
「なーんだ、やっぱり起きてたじゃないっすか」顔がにっこりと笑みの形になる。
「目の下にクマ作って夜更かしが得意そうに見えるわりには、ダメなんすね」
「るせー、ちょっと考え事してたんだよ」
「寝たふりしながらっすか?」
「……るせーな。そー言うお前は何でそんな楽しそうな顔してるんだよ、気持ちワリィ」
先ほど起こって眉間にしわを寄せながら近づいて来たのにもかかわらず、ぱっと表情を変えた青沼を怪訝そうな顔して覗き込んだ夏葉は、ゆっくりと体勢を変えてソファーに座りなおした。
「いやぁ、何かやっぱり、夏葉先生は腐ってもみかんだなーって思って」
「腐ってもみかん……?」
ついに徹夜だった夏葉はボーっとする頭で青沼の言った事を理解しようとしたが、うまくいかない。考えることは早々諦めて天井を見上げた。
「だいいちよー、兵士と同じように担当教官も三交代にしろって言うんだよな……」
「兵士さんたちは俺たちと別なんすよ。彼らが夏葉先生みたいだったら、いつ誰が脱出したっておかしくないんすからね!!」
「脱出……ねえ……」
夏葉は生徒詳細の紙束をみつめて何枚か紙をめくった。そのページには工藤依月(男子5番)と郡司崇弘(男子6番)の顔写真と彼らの詳細が印刷されている。日が落ちている間は音沙汰なかったが、このクラスで唯一脱出を考え、そして未だに生き残っているグループだった。
「あ、やっぱり工藤君たちのことっすか?」青沼も興味あるのか、ひょいと覗き込んできた。
「ああ……。一応このエリア28には脱出の手助けになるようなものは一切置いていないはずだけどな。盗聴記録あさってみろ、多分奴らてこずってるはずだから。でもな……あいつらなら他のもの代用するのも考えられなくは……ないけどな。わかんね」
夏葉はあごに手を当ててうーんとうなった。工藤は市内一位の進学塾でトップの成績らしいが、肝心の授業は「面倒だし、つまんないから」と言って屋上に消えていく。高校受験には内申も必要だ、と何回諭しただろうか、それでも塾のほうのコネで私立進学校の特待生になってしまった。夏葉の(いい加減な)説得も、水の泡となったというケースだ。
一方の郡司はきちんとした優等生の模範のような生徒だった。外見がだらしない工藤と違って、寝癖こそは爆発しているとしても身だしなみもしっかりしている人間である。工藤とは別の公立高校に合格したが、やはり県でもトップクラス。体育以外はすべて成績5で通過した。
何度彼らの経歴をその目にしたか覚えていない。ただ、目の前の資料に書き連ねてある輝かしきエリートの道を見ていると、どんでん返しがあるかもしれないと疑うのが普通の人間だ。
「でも工藤君とか郡司君は首輪に盗聴器が仕掛けられてて、話したことが全部こっちに筒抜けだなんて夢にも思ってなさそうっすね」
「はっ、哀れなやつらだよな……」
それとも首輪に盗聴器があることを知っててあえてそういうネタを振ってこっちをごまかしている?本当は、もっと別のことを考えている?いや、それとも本当に脱出する手立てがなくて何も話さない?――資料を握る夏葉の手にぎゅっと力がこもった。
「なぁ、そういえば青沼。お前覚えてるか? 去年あたり……プログラムから脱出した奴らがいて、世間がかなり騒いだやつ」
不意打ちのように問いかけられ、青沼は「えっ……ああ、覚えてるっすよ」と答えた。
「そんな風になりたくないんだよなー、ぶっちゃけ、あとの処理がめんどくさいし。だからよ、考えられる最悪の事態の芽はすべて摘み取っておくのが一番だと思わねえか?」
「最悪の事態……すか?」
「ああ、備えあれば憂いなし……熟慮の結果論ってわけだ。次の放送のあと……12時の放送までには特例を敷く」
特例、その言葉に青沼の目の中の光の色が変わった。
夏葉はそれをちらりと見て、それでも見て見ぬ振りをする。何枚かの紙束をぎゅっと持ち上げ、付箋がしているところまで飛ばす。ぺらりとめくったところは、蓮川司(女子9番)のページだった。
「……また蓮川さん見てる……」
あきれたように青沼が言う。だが今はもう、彼の瞳にはいつもどおりの光が宿っていた。
「こいつ、優勝すると思うか?」
「さぁ……一応俺は蓮川さんに賭けてるんすけどね。でもどうでしょう……殺害人数が1位だからって、優勝するとは限らないっすよね。だって、どんな人間にも『絶対』なんてないんすから」
「……ハハ、お前が言うと笑えないのは何でかな」
空笑いをした後、夏葉は資料を床においてまたソファーにゴロンと横になった。置かれた資料を見て今度は青沼がうなる。
「しっかしまぁ……変な子がいるもんっすね。俺、24年人生やってましたけど、初めて見たっすよ、こんなにすごい考え方と強い信念持った子」
「はっ……中学生だって人の子だあ、裏の心があったってなんらおかしくねえよ。お前はずっと人の表ばっかり見て育ったんだろ、どうせ。だいいち善人ばっかりのプログラムなんて、俺は担当したくないね。タイムオーバーで全員爆死だよ」
肩をすくめておどけてみせる夏葉に、青沼は手を口の前にやる前につい噴き出してしまった。一応上司である人間を笑うなんて、とその1秒後にすぐ理解したのだが時は遅し、クマの出来た目で笑ったな、といわんばかりにギロリと睨まれた。それもなんとか一瞬で終わったが、また夏葉はやる気のなさそうに青沼に背を向けた。
「お前、資料持ってんだったらよく見てみろ。少年院行きのことは書いてあんのに、原因は書いてないんだ。変だろ? それに禁止エリアになるかもしれない、見張りの人間の持ってるクルツで蜂の巣にされるかも知れないっつーのにあいつは私物の我が闘争を取りに来た。聖書並に大事にしている我が闘争、それから自身をヒトラーとして、敵をユダヤ人とする思想……ほらな、あのガキが化けるだけの要素は揃ってる」
「化けるっすか……そういえば彼女、ここまで何度か化け物扱いされてるっすよね?」
「人を平気で殺せるようなやつは、はたから見たら忌むべき化け物に見えたって事だろ? 俺だって他のやつらの立場なら普通にそう思うしな。だいいちアイツにはクラスメートなんて言う他人との関係はほとんどないだろうし。未練もなけりゃ悲しみもない。なんせ他人なんだからな……」
それからは2人とも口を開こうとはしなかった。そうしている間にも放送の時間は近づいてくる。
「青沼ァ、お前、次の放送やってみろよ」
「ええ?! 俺がっすか?」
「オメーもよ、もう次で独立だぁ……お上にそう伝えとくぜ」
何でまたいきなりそんなことを――唐突に言われた独立宣言。まだ一応は見習いとして副担当教官を担っているのだ、本当の担当教官ではない。夢であったプログラム担当教官になれたということは嬉しいのだが、普通こんなところで言うだろうか。さまざまな思考を張り巡らせて見たが、ひとつの結論にたどり着いた。
「ただ自分が放送するの面倒なだけじゃないっすか……」
青沼に背中を向けソファーに横たわった夏葉は、はじめの時同様、うんともすんとも返事をよこさなかった。
「もう! 知らないっすよクビになっても! オレの所為じゃないっすからね夏葉サン!」
ぴしゃとドアを乱暴に閉めて階段を下っていく音が反響し、夏葉の背中に当たって跳ね返る。むくりとまるでナマケモノか何かのようにゆっくりと仰向けに体勢を変えると、ふぅとため息をついた。
「ハハ……ガキの心なんてわかってたまるかよ」そう、自分に言い聞かせるようにつぶやく。
遠藤雅美(女子2番)と諸星七海(女子14番)が死亡したので、残りは名前の順に相澤圭祐(男子1番)・市村翼(男子3番)・工藤依月(男子5番)・郡司崇弘(男子6番)・榊真希人(男子7番)・新宮響(男子9番)・千田亮太(男子10番)・森井大輔(男子15番)・柏崎佑恵(女子3番)・蓮川司(女子9番)の10人となった。このうち9人が死亡し、優勝者が決まる。今日中には終わるだろう、そう考えた夏葉は汚れが染み付いた天井を見上げながら、またため息をついた。俺も年食ったかな――ため息ばかり充満して、若さのかけらもない。
ベージュの革ソファーは冷たかった。夏葉はゆっくりと起き上がると、近くに用意されていた毛布を掴み、それをかけてまた睡眠に落ちていった。
残り10人
Next / Back / Top
