朝6時の放送で、いっちゃんの彼女の遠藤雅美さんの死亡が告げられた。まあ君とは一度はじめのほうにF−07で出会っている。そのときはやっぱりいつものように怒ってた。いっちゃんもまあ君も、とても不器用だと思った。どうして自分の気持ち、ちゃんと伝えられないんだろう……。
いっちゃんはそのことを後悔してるのだろうか、ずっと無口のまま歩いている。脱出しようにもちっともいいものは見つからない。こんな原因があるからイライラしているのかもしれない。もっと俺が頑張ればよかったんだ。俺がいっちゃんと一緒にいることで初めて自分の能力を生かせると言うことに楽しみを見出しているだけじゃなくて、もっともっと真剣に脱出しようと思わなきゃいけなかったんだろうと思う。
脱出――心の奥底では、夢物語だと分かっていた。でも俺は、それをやろうとした。その必死さが欠けていた。だけどそれもやっぱり無理かもしれない。さっき流された夏葉先生の臨時放送は、衝撃的だった。行動できるエリアを砂浜のほうの4つのエリアにしてしまうと言う悪夢、つまりそれは脱出が事実上不可能になると言うことだ。更に悪いことといえば、雨が降ってきたことだろう。かなり寒い。
俺たちは、どうすればいいんだろう。でも俺は、いっちゃんについて行くしかないし、それだけで十分だ。もう一度、原点に返ってみよう。どうして俺がいっちゃんのあとについているか、思い出そう。
俺はいっちゃんと一緒にいることに、ちっとも後悔なんてしていないはずだ。
10:02
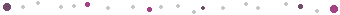
夜中の間中ずっと脱出に必要ありそうな物資を探索したり、このエリア28を区切っている金網や見張りの兵士を見に行ってみたりと、本来なら休息を取る時間帯にもかかわらずせわしく動き回っていた。馬鹿みたいに躍起になった割にはなんの進展もないことに、脱出の発案者である工藤依月(男子5番)はこの上ないほど苛立っていた。集まらない物資、穴だらけの杜撰な計画、減りゆく生徒と時間。それらは工藤と連れの郡司崇弘(男子6番)の精神に大打撃を与えるには十分だった。
2人ともかつては学年でも郡を抜いて頭脳明晰だった。だからこのプログラムを脱出する位、訳無いと踏んでいたのだ。去年辺りのに話題になったプログラム脱出――本当に脱出できたなら、彼等に出来て自分たちに出来ないわけがない。だって俺達はこの頭脳が売りなんだから――と工藤たちが考えてしまうのも無理はない。そういった自分の頭脳に対する矜持が、工藤を急かしていた。
早くしないとチャンスは消えうせてしまう。折角希望の光りが見えて着たのに――そう考えては、また苛立ちを重ねていった。
そしてまた、先ほどから降ってきた雨が更にイライラに拍車をかける。傘などはあいにく持ち合わせていないため、当然ずぶぬれだ。タオルなどももうないから、ブレザーを頭からかぶるしか雨よけの方法はない。かといってどこかで雨宿りなどしている暇はないから、体温が雨に奪われるのを黙認しながら歩いていくしかなかった。
「いっちゃん」
先ほどから何度も郡司が背後から工藤を呼び掛けても、工藤は振り向かなかった。否、正確に言えば振り向くだけの資格は彼に与えられていなかったのだ。
そもそもの理由は全て先ほど流された放送にある。夏葉翔悟(担当教官)が流した緊急放送とやらで告げられたのはエリアの縮小――4つのエリア以外は全て禁止エリアになってしまうというやつだ――それは工藤が考えていた計画を全て台なしにしてくれた。
生きるためのたった一つの希望だったこの計画がおじゃんになったことに、工藤はここまでついてきてくれた郡司に多大なる迷惑をかけたと思っている。しかしそれでも怒る事なく黙って後ろをついて来てくれている郡司を見れば、その姿に泣き付いて弱音を吐いてしまうかもしれないと思う自分がいた。
「ねぇいっちゃん」
また、振り向くことが出来ない理由はもうひとつあった。工藤の彼女だったあの遠藤雅美(女子2番)が死んだという放送が朝の定時放送で流れ、その影響で目頭を赤くしていたのだ。郡司は幼なじみの藤原優真(男子11番)が死亡したと放送で呼ばれても絶対に涙を見せなかったのに、自分が泣いていては情けない、それを隠すためになかなか振り向こうとしなかった。
ぐいと郡司の手が白いブレザーの裾を引っ張ってやっと、工藤は振り向いた。焦りと羞恥と絶望が入り交じった情けない表情をして。
「……タカは……俺に失望したか?」
サアアと地面を打つ雨音に混じって、工藤がボソリとつぶやいた。数え切れないほどの謝罪の言葉を凝縮して出来た言葉がこれだったのだ。
「馬鹿みたいだよな。よく考えてみたら、脱出に必要なものを置いておくような夏葉じゃねえよ」
郡司が何も言わないのを確かめると、工藤は溜息をついて俯いた。
「だけどこれだけは信じてくれよ、な? 俺は、タカと一緒なら絶対に脱出できるって確信してた」
その確信も禁止エリアが広がることによって打ち砕かれたのだが。どうしていいのか分からずに路頭をさ迷って、揚げ句の果てには混乱したなれはてを、しかし郡司は焦りとは裏腹に優しい瞳で工藤を見、肩に両手を置いた。
「俺はずっと脱出できて生き残れるからいっちゃんについてきたわけじゃなくて、ただ脱出の計画を話す堂々としたいっちゃんがかっこよかったから俺はついてきたんだ。俺もずっといっちゃんを信じてたよ。どんなに落ち込んだって、またいつものような面白くてかっこいいいっちゃんが戻って来てくれるってね」
にこりと笑い、ね?と念をおすように首を傾げると、郡司の寝癖が雨に濡れたままぴよんと動いた。いつものいっちゃん――いつも通りにしていた気がするのだけれども、他人に言われるとやはりそうなのだろうと実感する。
しかしだとしたらどうすればいい?という疑問に突き当たる。脱出計画が潰れた今、このプログラムの約束通り、最後の一人になるまで殺し合うということを遵守するしかなくなるのだ。いつか誰かと遭遇して殺されそうになるかもしれない。いつかこの二人が敵として対峙することもあるかもしれない。こんな状況で、平和に溺れ、守るべきものを知らず、ただ雲が流れるように日々をただこなしていただけの工藤依月に戻れるか自信は無い。
「だから俺は」
付け加えるように郡司はまた口を開いた。
「俺はそんないっちゃんが戻ってくるまでずっと待ってる」
郡司が優しいだけの人間ではないという位わかっていた。何せあの短気で喧嘩早い藤原遊馬をなだめていたという実績があるくらいだ。郡司と同じ塾に通い続けていた工藤もその能力を見落とすほど洞察力がない訳では無い。だが今回の一件ではに自分の命がかかっている分、事実上破綻に陥ったこの計画にさすがの郡司でも憤怒するかと思っていた工藤には少し拍子抜けだった。
「うん……サンキュな、タカ」
照れ臭さを隠すために工藤はふいと顔を背けた。
「とにかく先にあのエリアにいっちまおうぜ。一応制限時間はまだあるんだから、何するかゆっくり考えよう」
「そうだね。そうしよっか」
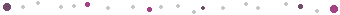
それから15分弱かけてようやく目的地のエリアにたどり着いた。時計は午前10時15分ほどを指している。
「砂浜だ……海の家っぽいのも見える!」
郡司が向こうのほうにある海原を指差した。水滴の潜熱で指先からは完全に熱がなくなり、本来の肌色からかなり遠い色になりかけている指が、奇妙な色に染まって見える東京湾のほうを向いた。彼らのいるほうが高台に当たるのか、眼下に広がった砂浜や海の家が一望できる。そろそろこの辺りが例の禁止エリアにならないエリアだろう。工藤はほっと肩の荷をおろした。10時15分ちょっとすぎ、舗装された道路に沿って真っ直ぐ南下してきた甲斐があった。道路が西側にカーブしているあたり、ここがG−07エリアなのだろう。もう少し足を動かす必要があった。残りは15分……雨もまた、一段と強くなってきた。
「まだ喜ぶのは早いぜ。海の家が集まる集落までダッシュだ」
工藤は郡司の手を握り、雨の中滑りそうなアスファルトを踏み出した。余計な概念は取り込まず、ただひたすら禁止エリアにならないエリアまで駆け出すことだけが精一杯だった。二人の冷たい手が重なって、さらに冷たくなったように思える。それでも興奮からおこる脂汗か雨滴か分からない液体がその掌の間に存在していた。
あと何百メートル走らせれば気が済むのだろう。工藤はそう考える。偶然近場にいたからいいものの、エリアのはずれのほうにいたならどんなに頑張っても体力が並かそれ以下の2人にはきっとかなり難しい状況に陥っていただろう。クラスはおろか学年で一番足の速い市村翼(男子3番)の能力が今だけ羨ましいとさえ思った。郡司においては元々そういう能力が欠如していたからしょうがないが、工藤はやれば出来る体質だったのに、やらなかったから出来なかった。やっとけば良かったな、と今頃後悔する。後悔する時がこんなにも早く来るなど、微塵にも思っていなかったが。
しばらく走ると道がもう一度ぐにゃりとカーブし、もう一度南のほうへと向き始める。頭の中に叩き込んだ地図とその地理を照らし合わせると、どうやらG−05まで移動してくれたらしいと言うことが理解できた。無事なエリアはG-04、G-05、H-04、H-05の4つだ。何とか安全地帯に入ったらしいと認識すると、海の家が見える場所まで走り続けた。
コンクリートにたまった水溜りを踏みつけると灰色のズボンに尾車と泥水が跳ね上がった。だがそれもお構いなしに工藤と郡司は走り続ける。
「……着いた。ここなら……大丈夫だろ……」
久々に全速力で、しかも長距離走り続けたために、心臓が不協和音と言っていいような鼓動を奏でていた。肋骨のところに手を押し当てると、心臓の音が嫌というくらい聞き取れる。はぁ、はぁ、とあえぎ、肩を上下にして新鮮な空気を懸命に取り込もうとした。空気から酸素をうまく分配し、脳に足りていなかった物質を配給する。そしてからようやく、彼らが誇りに思っている頭脳が回転し始めた。
「そう……だね」
工藤はまだマシにしろ、郡司はかなり疲労を感じているようで、膝に手を当てて全身で新しい空気と古い空気の循環をしているようだった。大丈夫か?と工藤が声をかけても、なかなか返事を寄越さない。呼吸するのに精一杯なのだ。
「時間はあるから、ゆっくり深呼吸しろよ。この辺りなら、誰も――」
工藤が郡司の背中をさすりながら辺りに誰もいないことを証明しようとし、背を伸ばした瞬間だった。自分たちが身体を向けていた方向、つまり南の方角にもうすでに先客がいたのだ。工藤の目に映っていたその人物は、何かを手にして真っ直ぐこちらを向いていた。
「逃げるぞタカッ!!」
まだ回復しきっていない郡司の腕を無理矢理引っ張って、工藤は手近な海の家まで全力疾走した。
「えっ……ど……どうしたの?!」
さらなる運動を求められたので郡司は困惑した。
「千田が……アイツは絶対俺たちの事を狙ってる!!」
嘘だ、と否定しようとした郡司の脳裏を一瞬だけ千田亮太(男子10番)の姿がかすった。太い黒ブチめがねと坊ちゃん刈りが印象的なのはクラスメートは当たり前のこと、学年全員が知っていることだ。流血や犯罪、そういったグロテスクなものを一番好んでいる不思議な少年であることも然り。工藤はそんなイメージから千田が襲ってくると理解したのではない。千田が拳銃を構えて今にもこちらに発砲してきそうな格好をしていたのをその目で見たからそう判断したのだ。案の定、郡司の否定は数発の銃弾によって破棄される。
パンッ!!パンッ!パンッ!……
「ひゃっほーい☆ 工藤とタカちゃんみーっけぇーっ」
銃声と共に聞こえてきた実に軽快な声色は、彼が分校を出発するときから何ら変わっていない。むしろあのときよりも余裕を感じさせられる。何でアイツはあんな余裕ぶってられるんだよ、おかしい、おかしすぎる!!――工藤は焦りの絶頂を迎えている自分とは裏腹に、心底余裕に浸っている千田を疑った。何か決定的に勝てると言うものがあるのか、それともただ単に馬鹿なのか……答えの候補はまだまだありそうだった。
銃声が一旦途切れたが、郡司も工藤も必死になって走り続けていた。
不幸中の幸いか、このすぐそばには海の家らしい建物が点在している。バリケードさえあれば白兵戦よりはずっと楽だろう。彼らは体力を使い果たした身体に鞭を打っては足を動かし続けていた。
そんな彼らを追いかけているのは千田――彼もまた、お世辞にも足が早いとは言えない――だ。しかしいろんな意味で満身創痍、身体的にも精神的にもダメージを受けている工藤や郡司と違い、千田はそれほどでもない。彼は先ほどG−07から避難してきたばかりだが、その前に榊真希人(男子7番)に遭遇し、射殺している。榊のバッグを荒らしたところ出てきたのはロープ一本。最後の終盤戦を乗り切るための武器を得ることが出来なかった千田だが、普段の生活では越えることの出来なかった一線を越え、本物の流血、リアル感を追い求めた彼には武器の代わりにこの先も精神を安定させられるほどの恍惚感を与えた。
そんな快楽で満たされている千田が疲れなど稚拙な感情を感じるわけもなく、したがってこうして笑いながら工藤たちの後を追うことが出来ると言うわけだった。
そんなことはつゆ知らず、工藤は常時笑みを浮かべる千田をちらちらと見ながらも郡司の腕を引いて近くの海の家まで走った。何とかバリケードを用意したかったのだ。既に郡司は体力の限界を迎えているらしく何度も倒れそうになっている。
「もう少しだから、頑張れタカ!」
工藤も比較的余裕があるにしろそれでもかなり限界に近い。人一人を引っ張って走るのは、重い荷物を担いで走るのと似ているからだ。彼もまた喉に血の味を感じながら奥歯を噛み締めた。
残り9人
Next / Back / Top
