1999年3月18日。晴れ。少し強い空っ風が吹いていた。今年は桜が時期はずれなほど早くに咲き乱れている。風に乗って花びらが舞う姿はいつ見ても美しくあり、それでいて儚くあった。
だがそんな幻想的な風景とは相反して、まさか司が中学校の卒業式に血まみれの制服で出席したなど夢にも思っていない蓮川家の息子達は、今日も緊迫した朝を迎えていた。
朝が来て目覚めると、まず始めにため息をつく。ああ、今日も生きている。今日もまた必死に生きる一日が始まるのだ、と憂いながら。
司が優勝したと聞かされた日からずっとこの調子だ。例えいないとわかっていても、どこからか彼女の視線がまとわり付き、絡み付いているような気がしてしょうがないくらいに罪の意識にさいなまれている晴一、貴正、時哉の3人。いつもの堕落した生活は訪れず、生きていることを一日一日感謝する日々が続いたのは生まれて初めてのことだったために、戸惑っていた。
朝。彼らの住んでいる千葉県高原市から離れた私立高校に通っている時哉が家を出て行く時間が訪れた。彼は小学校のとき地元の小学校に通っていたが、絹のように見事な色白の肌と色素の抜けた髪の毛を馬鹿にされ、いじめられたので中学校・高校は噂の届かないような遠くの場所を選んだのだ。彼がイジメの噂に怯えながら暮らす生活に終わりを告げるためには、そうするしかなかった。しかし今度はどうだ。確かにイジメの噂は距離と比例して薄くなっていったが、血のつながった妹に殺されるかもしれないという恐怖は、いつでも、どこにいても、拭い去ることは出来なかった。
「時哉、弁当」
キッチンのほうから差し出された長兄・晴一の手に握られたのは青いナプキンにくるまれた少し大きめの弁当箱。県下でも最低ランクの学校の、最低レベルの不良息子も、限られた小遣いを無駄にし、カッコつけてコンビニ弁当を買うよりも、兄に弁当を作らせるほうがよっぽどマシだったようだ。時哉は「ども」と社交辞令気味に挨拶すると、そのままリュックに入れた。
時哉はそのまま玄関に行き、かかとが踏み潰されたローファーに足を突っかけた。戸を開けて外に出る。白くぼやけた青空が見え、赤とオレンジの薄いグラデーションが住宅街の上を彩っている。駅までの自転車の道のりの中、マフラーはいらないか、と気温の高さに少しほっとした。玄関の横に止めてあるマウンテンバイクにまたがり、石畳の大理石の上を無遠慮に駆け出した。背の高い豪勢な門の内側に設置されているボタンを押すと自動的にロックが開く。開錠し、門を開いて進行方向へと自転車の先を向けた。
ふといつもの情景に違和感があるのに気付いた。
何かが違うのだ。いつもここから見える道は、左手側には2メートルほどの白く高い壁、それからその上についている紺色のかわらが続く蓮川家の壁、右側には他の家の垣根やガーデニングの施された庭が見えるはずなのだが。それでも今日は違う。何が違うかをよく目を凝らしてみてみた。
プログラム優勝者
ただの殺人鬼
文字の羅列がカラースプレーで白い壁と言うキャンパスに汚く(しかしえらく馬鹿丁寧に)殴り書きされていた。
死神。残酷。友達をかえせ。死ね、死ね、死ね、死ね。消えろ。
いくつもの中傷罵倒の言葉が、時哉の目に映ったそのとき、彼は自転車からずり落ちそうになった。
「……なんだよ、これ……」
とりあえず家の前の道路に面しているところに見える白い壁のほとんどが、カラースプレーの文字で埋め尽くされていたのだ。
ザッ……と急にかどのほうから自転車を動かす音がした。
「誰だ!!」
時哉はすぐさまその影を追うが、後少しのところで逃げられる。その姿は、白い服。今春中学に上がる四男の真人が新しく買ったと嬉しそうに着ていた、あの高原第五中の白い制服だった。
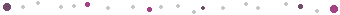
そのあと、慌ててリビングに吹っ飛んできた時哉を落ち着かせながらも、しかしこの壁をどうするか晴一は悩んでいた。蓮川の家は広いため塀も長く伸びているが、そのほとんどが落書きに包まれている。
警察に被害届けを出すか。それとも時哉が見たと証言する高原第五中に訴えに出るか。だけどそんなことをすればしないでも有数の金持ちがこんな無様な様子になっているという事を世間に見せ付けてしまうことになる。これでも一応まだまだ蓮川家はお金持ちでやっていけているのだから、これはきちんと処理しなければいけない。
はぁ、と無意識のうちにため息が出た。朝から炊事、洗濯、掃除、アル中の父・修造の世話、バイト、帰ってくればまた炊事、片付け、といっぱしの主婦よりもハードスケジュールを組み立てている晴一にとってこれらは悩みの種でしかない。かといって貴正や時哉、ましてや弟の真人や洋介に任せるわけにもいかない。結局は何もかもが自分につけが回ってくるのだ、と半ば諦めながら晴一は今一度カラースプレーで中傷誹謗の文字が書かれた背丈2メートルほどの壁を見た。
『化け物』が『人間』の人生奪っていいと思ってるのか
思わず目をそらしてしまった。
なぜ人々がこんなことを書くのかすっかり分からない。第一どうして司がプログラムで優勝したことをこの界隈が知っているのかすら理解できないのだ。それらの疑問は取り合えず別に考えるとして、晴一は化け物と書かれた部分に手を触れた。
化け物とは、司のことだろう。なんとなく察しがついた。
だとしたら、これを本人に見せてやりたいと思った。いつ来るか、いやその前に何が起こるか検討もつかない“司の復讐”とやらの第一歩がこれならば、きっと彼女はどこかでこの光景を見て細く微笑んでいることだろう。彼はそう考えた。そして苦しんでいる俺たちの姿を見て、のた打ち回るくらい笑っているに違いない、とも。
彼らに残された選択肢は、世を憂うか、己の罪を呪うかのどちらかしかないようだった。
3月20日――司がプログラムに優勝したと聞かされて5日が経った。結局晴一は父親の修造に相談することもなく壁の落書きのことは警察に届け、高原第五中学校にも訴えることにした。壁は発見した翌日に業者に来てもらって塗りなおしてもらったのだが、また次の日に新たな落書きがされていたことからこの決断に至った。しかも今度は『中学生ぐらいの子が書いていた』という近所の人の証言もある。結局その人に手伝ってもらって両方に訴えることとなった。もちろん中学校のほうで犯人が割れるはずがない。むしろ逆に学校の校長からは何か言いたげな素振りをされたのだが、直接訴えてこないのでわずかな疑問だけが残り、結果的にしこりのあまる訴えとなった。
そのこともあってか、以来外に出ると冷たい目で見られるようになった。落書きのことはもとより、司がプログラムで優勝したことも自然と近所の住民などに露見してしまったらしい。そういえば一緒に証言してくれた近所の人も、常に愛想笑いを続けていたように思える。
晴一はそれらのことの処理に忙しく追われていたが、貴正も時哉も一日のほとんどを部屋の中ですごしていた。下の2人の弟である真人や洋介は、実の妹からの罪の制裁に怯える上の男兄弟と比べ、普通に過ごしていた。
だがそれも、うたかたのごとく消える。
その日、一番下の弟の洋介が泣いて学校から帰ってきたのが事の発端だった。
セキュリティの掛かった門を暗証番号で開けたことを示すインターフォンが鳴り、その後すぐに大泣きする声が聞こえたから、夕飯は何にしようか決めかねていた晴一、もう学年末試験も終わり授業がないからというずいぶん好都合な理由により学校に行っていない時哉が驚いた様子で迎え入れた。
「おいおい、どーした洋介」
涙と鼻水で汚くなったその顔にティッシュを押し付けながら時哉がたずねた。それでも洋介は何も答えない。否、しゃくりあげるほど泣いていたので、答えられなかったと表現するのが正しいかもしれない。
「違う……見ろ、時哉」
洋介の後ろ手に回った晴一は、驚愕と絶望が入り混じった表情を見せた。
人殺しの弟
殺人
死ね
姉ちゃんは殺人鬼
黒いランドセルに浮かび上がるベージュの文字。おそらくカッターナイフか何かで切り刻んだのだろう、典型的な『イジメ』とやらはまだ小学校4年生でしかない洋介を思いがけず襲った。
まともに話せないほど洋介は声を張り上げてむせび泣いた。元々末っ子で泣き虫だったところもあったが小学校に上がったこともあってか、今までそれ程酷くは無かった。しかし今回はどうだろう。ホラー映画のビデオを見て絶叫しながら泣き出したときとはまた違う涙だった。
「……ガキだな」
洋介のランドセルに視線を落としながら時哉がボソリとつぶやいた。彼もまた小学校のときにじめられていたが、それとはまた別に種類である。時哉は身体的にいじめを受けていたが、こちらは昼ドラマ宜しく精神的なイジメである。実際、洋介の身体にひとつも傷はついていない。その昔、時哉はアザだらけで家に帰ってきたこともあったと言うのに。それでもどちらが深く傷ついただろうか。犯人があからさまに分かるいじめと、分からないいじめでは。
彼のつぶやきにに答えるかのように、このイジメに対するものと取っていいような舌打ちをした晴一は、「当たり前だろ、ガキなんだから」と更に付け加えた。
世間一般で話題になるイジメとやらがつい先日まではあんなに遠かったのに、一瞬にして間近に置かれるといささか困惑する。被害者の母親などが匿名でテレビに取り上げられたりするが、その苦悩の気持ちも今なら分からないわけではない。
が、ひとつ兄たちには疑問が浮上した。
「なあ、何でこいつら司がプログラム優勝したって……ていうか人殺しだって知ってるんだ?」
時哉が晴一に対して尋ねた。晴一も晴一で俺にそんなこと聞くなよ、と言わんばかりに眉をひそめる。
「みっ、皆……中学校の、卒業……式ッ、でっ……司……姉ちゃんがっ……来たって……テレビでっ……も……やってた……し」
代わりに答えたのは被害者である洋介だ。教室で洋介の事をちらりと見ながらひそひそ話をしていたのを偶然聞いたのだ。それは確かに、聞こえよがしに大きな声で話していたのかもしれないが。そのとき聞いた情報を兄たちにそのまま伝える。
「中学校の卒業式? どういう事だよそれ!」
しゃくりあげながら話す洋介の肩をぎゅっとつかんで乱暴に揺らした。止せよ時哉!と長兄が止めに入るが、司の名前が出たことで一瞬にして周りが見えなくなった時哉の暴走はとまらない。
「だってあいつ、病院に入院したって……卒業式なんか……出れるはず……ない、だ、ろ?」
ハハハ、と乾いた笑いをこぼす時哉の目は、大きく見開かれて視点を定められなかった。まるで幽霊を見たかのようなその目に正気沙汰は映らない。しかし彼の言い分はもっともである。テレビの映像を見た限りでは白い制服を血まみれにして、いかにも重傷だといわんばかりのものだったが、もしそれが本当に重症だったら卒業式なぞいける状態ではなかっただろう。だいいちこの家に優勝報告をしに来た政府の人間が、確かに『左肩に銃弾を受け――』と言ったはずだ。それでもぴんぴんしていると続けた政府の男の言葉を思い出す。出来ない可能性がゼロではないだろうと考えられた。
もしや、と晴一は指を口に当てる。次第にカタカタと震えだした口を押えるかのように指を唇に押し付けた。
――まさか、左肩以外のあの血はクラスメートの血……?
二の句が告げない3人が黙り込んだとき、続いてもう一回、セキュリティを解除し、正門から家の中に入るインターフォンが鳴り響いた。しばらくした後、音も立てずにドアが開く。四男の真人だった。真人はランドセルのふたの部分を自分の胸元にくっつけるようにして抱きつつ扉を開け、そっと入ってきた。とりあえずすぐに自分の部屋に行こうとしたのだろう。広い玄関の大理石の箸に自分の靴を置いて階段のほうへと以降とした瞬間、凝視し続ける兄弟の視線にようやく気付いたようだった。
「あ……た、ただいま。晴一兄、時哉兄、洋介……どっ……どうしたのさ玄関前で……」
あからさまに態度が違うのは、見て取れた。まだ卒業前の小学生で、その上真面目で根っからのいい子だから嘘さえもうまく操れない。それが純粋な証拠だとしたら、胸元に抱えたかばんの有様はまるでその純粋を穢す猛毒のようなものだった。
「真人。お前ランドセル見せてみろ」
晴一がずいと近寄ってきて真人の腕からランドセルを取り上げる。ランドセルを取り上げられた真人はばつが悪そうに立ちすくんだ。
「やっぱりな……」
真人のランドセルは表面の部分にたくさんガムテープが張ってあるものだった。晴一は何の疑いもなくそのガムテープを剥がし取る。その下にはやはり洋介と同じように、誹謗中傷の数々が刻まれていた。カッターもあれば修正液もある。
ふと、長兄は玄関のエントランスを見た。ルームシューズ、学校の上履きがそこにある。
「真人、上履きで帰ってきたのか?!」と問いただした。
「あ……いや、その……ほら、体育で靴が汚れちゃって……」
「普通上履きで帰ってくるか?」
「……えっと、先生が……上履きで帰りなさいって……」
時哉も晴一も、必死になって迷惑をかけまいと頑張っている真人の姿にため息さえ漏らしてしまった。察するところ、真人もまた洋介と同じようにいじめを受けていたのだろう。可哀想に、もう小学校卒業と言うのにも関わらず、その節目は笑顔で迎えられそうにもない。靴は大方隠されたか捨てられたのだろう。こちらも古典的で典型的なイジメの形と言っていい。
ああ、どうして罪のない弟達がこんなにも被害を被っているのだろうか?と晴一と時哉は悩んだ。それでも何の罪のない2人がこれだけなのだから、罪のある当事者はどれだけの罰を与えられればよいのだろう、と考えると身震いがした。
「何やってるの? 玄関前で」
ちょうど階段から降りてきた次男の貴正が、いつにも増して眠たそうな目をこすりながらやってきた。もう昼間も過ぎて夕方に近いと言うのに、今の今まで寝ていたのだろうか。そんなのんきな次兄に内心舌打ちした晴一と時哉は、階段のほうを睨みつけた。
「ちょうど良かった。貴正も来いよ」
洋介と真人の腕を引っ張ると、リビングのほうへときびすを返す。もれなく、時哉も来いと目配せで合図した。
「話したいことがある」
一番前を歩く晴一の背中が、やけに暗く感じたのはなぜだろうか。
晴一は真人と洋介のランドセルを食事の際に使用する長テーブルの上にどさりと置いた。それから上座の席からそれぞれの席に座った兄弟に「これ、どう思う?」と質問を投げかける。そう問われて訳が分からないと顔を見合わせたのは洋介と真人だけだった。
「……言い換えれば“何のために司が卒業式なんかに出たり、ニュースであんな事言ったのか”ってことだろ?」
珍しく時哉が正解論を冷静にはじき出した。
「その通り。結果的にそれがよそ様の兄弟とか噂で感染して、小学生の真人と洋介にイジメ、という形で伝染した、と考えてもいいだろうな。それにしてはずいぶん早い伝染病だけど……」
腕組みをしたままうーんと低く唸る晴一の左手側に座っている貴正は、その長い黒髪をいじりながら眠たそうにしていた。その我関せずの態度を見て、元の現況となった発言者がこれでいいのか?と晴一は疑問を抱いた。それでもため息しか漏れてこない。始めから貴正を相談の場に入れることが間違っていたのだ。部屋に引きこもり、小学校ぐらいのころからほとんど顔をあわせることのなかったこの弟を。そんな弟の『母さん、殺しちゃおっか』という提案を飲み込んだのは、紛れもなく自分なのだが。
だが弟達に対する私怨が妹の恨みを打破したり、軽減したりすることはない。平等に訪れるであろう罰に対して、さすがの引きこもりも日なたに出ざるを得なくなった現状がこれだった。
「で、結局何のためなわけ? もし俺たちが憎いなら、俺たちだけ殺せばいいはずだよね。怪我してるはずなのに卒業式に出たり、何の罪もない真人たちを巻き込むなんて、司らしくないとは思うけど」
相変わらず懈怠し、髪をいじっている貴正は逆にそう質問した。
「……分からない。まあ……あいつの考えなんてわかりたくないって言うのが本音だけどな」
「そりゃそうだ。誰が好き好んで人殺しの気持ちなんて知りたがるかよ」
晴一の回答に時哉が付け加える。だが今彼は完全に失態を引き起こした。人殺しの気持ち――それは自分が母親殺しの張本人だという事を失念した発言だった。当然のように長兄次兄からは鋭い視線が送られる。彼はばつが悪そうに視線を伏せた。
「だけど……どうにかして……真人と洋介だけはどうにかしてやりたい」
いやな空気が流れたところに口を挟んだのはやはり晴一だ。彼はちらりと真人と洋介を見ると、目線を引き戻した。まだ小学生という若さでこんな屈辱にも似た罰を受けるのはよくない。ならばいっそのこと――
「俺の案としては、こいつらをを養子に出そうと思ってる」
晴一の案はこうだ。母は死亡し、父はアル中でほとんど仕事が出来ない。唯一働ける長男はいまだフリーターもどきで、とても家族分を養うだけの財源は取れていない。よって義務教育の家庭途中である弟2人を養えないので、養子に出そう、と言うわけだ。養子でなくともただ単に“預ける”というのもいいだろう……ということだ。
「へえー、結構いい案じゃない? 父さんは一人っ子だから、父方の親戚っていないけど……だったら真人と洋介は母さんのほうのおばさんとかに預ければ?」
同じことを考えていたのだろうか、声色が少し乗り気になった貴正が付け加えて提案した。
「そうだな……俺もあんまりそっちのほうに訪ねたことないから快く引き受けてくれるか分かんないけど……明日行ってみて頭下げてみるよ。生活費は仕送りって形で工面するか。養子と言う形を取ってもらえば、蓮川の名前じゃなくなるしな。それなら別に俺たちがいつどうなろうとも関係ない……か」
「ちょ……ちょっと待ってよ! 誰も俺らがおばさんの家に行くなんて言ってないじゃん? だいいち俺、母さんのほうの親戚となんて一度も会ったことないし!」
真人が驚いた様子で立ち上がった。何よりもそれは疎外感を感じざるを得ないものだったからだ。確かに、真人と洋介はつい1日か2日前ほどに母と兄たちの間にあったすべてのことを初めて聞いた。そして姉がそれらについて知っていて、復讐せんとばかりにプログラムも優勝してくるだろうということも知った。結果的にいえば下の弟2人は、司の復讐に何の関係もない。だが将来もし、殺された際には必ず報道関係に大々的に蓮川の名前が流れ、そして蓮川という珍しい苗字をつけているだけで家庭事情に何かあったとうかがわせるには十分だろう。世間の目を考えてそれだけは避けたいと懇願する兄たちの気持ちも汲み取れず、真人は言い返した。立ち上がり、晴一の隣まで詰め寄る。
「俺だって蓮川の人間だよ! 下のほうだから家の事情なんて知らないけど、俺たちだけ別にする気? それだったら洋介だけにしろよ! 俺は絶対にいやだ! 俺は……晴一兄たちと一緒に残る! 俺を最後まで蓮川の家族でいさせ――」
真人が話しているところだったが、間を割って晴一のこぶしが飛んできた。平手打ちではない、その力強いこぶしが真人の頬に当たる。
殴られた本人だけではなく、他の兄弟全員がぽかんと口をあけたまま呆然とした。暴力的な父親の背中を見て、それに従ってきた晴一が、父親の命令ではなく私情で人を殴ると言う行為などみせたことなかったからだ。
「バカヤロウ!! 俺たちについてたって何の得にもならねえし、むしろ死ぬだけだって分かってんだろバカが!」
今まで落ち着いた様子を守ってきた晴一が、突然大声を張り上げた。
「法律には血縁家族は扶養しあう義務がある。おばさんたちが拒否すれば訴えて義務を与えることだって出来るしね。それにまだ義務教育中の2人なら、何とかできるでしょ。自立出来る俺達を養うのから比べたらね」
驚きをまだ残しながらも、自分だけは冷静になろうと視線を伏せながら貴正がつぶやいた。
「俺たち……いや、少なくとも俺はここに残る。俺が長男として課せられたのは、父さんの代わりに一家の家督を勤めることだ。何をやられようとも、俺はこの家を守らなきゃいけないんだよ……そうやって育てられて、そうやって生きてきた。それに引き換えお前たちは自由だ。金は俺が工面するから、おばさんのとこに行くなりバイトして稼いで高飛びするなり、好きにしろ」
罰を受けるのは俺たちだけでいいんだ――罪もない弟達を巻き込むことを極端に嫌がる晴一は、頭を抱え込んで押し黙った。黙っていても貴正と時哉は金を工面してこの家から逃げ出すだろう、特に司の復讐を恐れている三男坊時哉については絶対そうだと言い切れる。だから経済的にも社会的にも弱者である真人と洋介の逃げ出すための援助の助けは晴一がしてあげなければならなかった。それが簡単な道かと問われればもちろん答えはノーだ。かの有名なエベレストを登るよりも辛くて険しいものとなるだろう。それでもやり遂げなければならなかった。
「ごめんな……ごめんな真人、洋介。悪いのは、全部俺たちだ。母さん殺した俺たちが悪いんだ」
晴一がそう呟く。貴正も時哉も同様に視線を伏せた。
元はといえば自分たちが起こした憎悪からの母親殺しが事の発端で
罪の重さに苛まされるのが少しばかり遅かっただけなのだ。
これより先は、その重すぎる罰に身をすり減らしていく人生が始まる。
Next / Back / Top
