数ヵ月後、それはちょうど夏に差し掛かり、毎日の日差しも強くなってきたときだった。
「はい、指動かしてみて」
女性の、しかもまだ若いように見える医者が蓮川司の左手を自分の手の上に乗せつつ指示を出した。司は無表情を保ったまま指を流暢に動かしてみせる。
「じゃぁ次、ひじをあげてみて」
これも言われた通りに動かす。
「そうね、もう大丈夫です。リハビリは終了でいいでしょう」
すくっと立ち上がると女医はカツンカツンと靴を鳴らして病室の窓のほうへと向かっていった。
「一時はどうなるかと思ったけど、何とか壊死しなくてすんだわね」
ニコリと司に向かって笑いかけてみるのだが、そこには本当に安堵したといわんばかりのため息さえ含まれていた。
実は司は、プログラム終了後、術後あまり衛生状況のよくない場所――そう、卒業式が行われていた体育館だ――に足を運んだため、傷口が開き、肩にある神経に傷がついたのだ。それでもこの病院で一日中リハビリを続け、今ではこうして医者にも認められるほどの回復力を呈示して完治した。
「もう、ここを出て行かなきゃならないんですか」
リハビリは家から通えばいいものなのだが、司はここにいることに固執した。なぜかと問われれば理由はひとつしかない。あの家なんかにいるくらいなら、野宿したほうがまだマシだから、だ。
「そうね……病人じゃない人を病院においておくほうもどうかと思うし」
そうですか、と誰にも聞こえないような呟きを残すと、司はベッドの上に座ったまま床を見つめた。
「迎えは青沼先生を呼んでおいたから、もう少しで来ると思うわ。荷物まとめておいてね?」
女医はそれだけ伝えると、白衣を翻して病室から出て行ってしまった。会話を聞くとなにやら少し親しげな間関係がありそうだが、実際はそうでもなかった。元来持ち合わせたその鋭い目つき、絶対に誰も信用しないという孤独への執着心、それからプログラムで15人殺害して優勝したと言う事実――さすがにプログラム優勝者を多く受け入れているこの国営病院でも、これほどの殺人者は恐れられていた。
誰もが目をあわそうとさえしない。しかしむしろ司にはそれが心地よかった。ようやく何ものにも縛られず生きることが出来る瞬間が出来るのだ、と。永遠にも似たプログラムと、地獄絵のような今までの人生。放り投げて生きるだけの器用さは無かったが、それらの恨みを消し去る方法を思いつくだけの頭脳は残っていた。
パタンとスライド式のドアを女医が閉めたとき、不意に笑いがこぼれる。プログラム優勝、無理強いにでも参加した卒業式、怪我の完治、プログラム優勝者へ託される生活保証金……すべてが、すべてが計画通りだった。
「はーすかーわさぁんっ! お迎えにきたっすよー」
女医が出て行ったすぐあと、入れ替わりで青沼聖が顔を出した。プログラム担当教官の補佐という地位にいたらしい彼は、どうやら夏葉翔悟のように学校の先生を兼任しているわけではないみたいなので、ずいぶん暇そうにしているところを司の送り迎え役に抜擢されたのことだ。
「待って、準備何もしてない……」
別に慌てる様子も無く、司はベッドから立ち上がった。約2ヶ月過ごしてきたこの病院ともついに別れを告げるときがやってきた。これから家に帰って、それから強制転校の手続きを取って宮崎に飛ばなければならない。あの家に一歩も入りたくないと言うのが本心なのだが、何も持たずに宮崎に行くのもなんだか気が引ける。その辺りは目を瞑るしかなかった。
「あ、じゃぁ正面んとこに車出しとくっすね!」
相変わらず微妙な敬語(それにしても、ずいぶん崩れた敬語だこと)を駆使する青沼は、ニコニコした表情のまま廊下を歩いていってしまった。夏葉と比べたら10センチほど違うのだろうその小振りな体つきを見送って、司は長く伸びた髪の毛にくしを入れた。
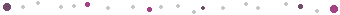
車は、極めて一般的な軽自動車だった。色は黄緑と白、いかにも若者が好みそうな車だ。助手席に座り、シートベルトを締める。負傷してリハビリを受けていた左腕はいっぺんの苦労も無くシートベルトを締められたので安心する。怪我をする前と比べると多少は劣るが、それでもかなり完全に近い。神経を傷付けられた割には器用に動いた。
「今日は……夏葉先生はいないの?」
別にたいした用事は無いのだけど、司はいつの間にかそう聞いていた。何だかんだでやはりあのうるさいのがいないとぱっとしたものが無い。
「夏葉さんはガッコーっすよ!」
「また私たちと同じオチ? 担任が担当教官って言う」
「うーん、どーでしょーねー。夏葉さんってばそういう事教えてくれないんすよ」
ハンドルを握ったまま話す青沼を一瞥した後、前を向いた。久々に見た住宅街の姿。信号があって、コンクリート詰めで、誰もがせわしそうに足早に歩くその光景。別にたいした面白みも無いのに、司はずっとその光景を見ていたいと感じた。信号が赤から青になって、流れるようにその光景が奪われると、なんだか残念な気持ちに陥る。
こんな起伏に富んだ感情を持ってたっけ――久し振りに病院以外の場所に出たからただ単にうずうずしているだけかもしれないと、自問を一蹴した。
「あの……蓮川さんって、夏葉さんのこと鬱陶しいとか、思ってたりするんすか?」
しばらく沈黙していたのを打ち破ったのはちょうど車が県道の信号で足止めをくらった時だ。
「……なんで?」
「あ、いや、ほら。最初っから思ってたんすよ。このクラスの子って皆先生に反抗的だなーって」
「まあ、ろくに授業やらないとか……誰かが授業サボってもほかの先生みたいに怒らないとか……私は別に嫌じゃないけどね」
そうっすかー、と少しほっとしたかのように胸をなでおろす仕草をする青沼はとても20代前半には見えず、どこかの高校生と見違えてもおかしくなかった。子供っぽいといえばそれはそれで正しい。
「あれでいて夏葉さん、本当は面倒見がいいんすよ! 俺にとっても、夏葉さんはもう一人の父親……ってか兄貴みたいな感じっす! 蓮川さんはどうっすか?」
「どうって……そんな事言われてもねえ、妻子持ちには興味ないし……それに……」
「それに?」
急に押し黙った司の語尾を重ねて青沼が聞き返した。
「……あんな父親とか、あんな兄弟がいたら、きっと私もうちょっとイイ子でいられたかもね」
自嘲気味にふふっと笑い、少し固めのシートに身を深くゆだねた。だけど、そんなイイ子ちゃんで育ったなら、今頃プログラムで死んでたかもしれない――付け足そうと思ったけど、それは心の中にしまっておくことにした。酒と性欲と男尊女卑と言う言葉しか頭に無い父親、実の母親を殺した兄たち、いつ裏切るか分からない爆弾のような弟。それらに誰かひとりでも夏葉のような人間が混ざっていたら、どんなに幸せあったろうか。絶対にありえない“もしも”を考えた。
もしも、普通の生活とやらを送っていたならば――。
もう、彼女は二度と泣かなかった。二度と人を愛さなかった。心から、綺麗な笑顔を浮かべることは無かった。
そのかわり
いつも口の端を吊り上げて笑った。その笑みは嘲笑の形を作っていた。人間味を失った彼女は、もう感情豊かな人間ではなかった。
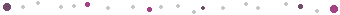
それからたいした会話も無く、高原市の少し郊外のほうにある蓮川家についたのは病院を出てから1時間しない程度のときだった。数ヶ月ぶりに見た我が家の周りを囲む背の高い壁が、以前は真っ白だったはずなのに今はところどころ汚れている。結構神経質な長兄がそんな汚れを見落とさないはずが無いのだが。しかしどうでもいいことなので彼女は視線をそらした。
「着いたっすよ!」
青沼が門の前で車を停め、ドアから降りた。彼にエスコートされる前に司はシートベルトをはずしてドアを開ける。それを見てすぐに青沼は次の行動、ドアのインターフォンを押しにかかった。心なしか、彼の笑顔が少し曇ったように見えたのは。
ピーンポーンと聞きなれない音がする。当たり前だろう、司はいつも裏門から入っていたので、生まれてこの方一度も正門に足を踏み入れたことが無いからだ。下の弟2人でさえ正面の門から入れると言うのに、司は裏門から入ることを余儀なくされていたことが理由のひとつにあげられる。
『……はい』
インターフォン越しにデジタル化された声が届いた。間違いなく、長兄の声だ。
「こんにちわー。政府のものですけど、妹さんの連れしました」
『……はい、少々お待ちください』
がちゃ、とインターフォンを切る音がして音が途絶えた。しばらくするとサンダルを突っかけてくる音が聞こえ、木製の豪勢な門が開いた。
「どうも……」
ずいぶん見違えるほどにやつれた晴一が門から出てきた。彼は力なく笑うと「お帰り、司」と彼女に話しかける。どうせそんなこと心にも思っていないのだろうと感じながら兄を一瞥すると、司は無言でその隣を通り過ぎていった。
ずいぶん態度が変わったじゃないか、それもこれもいつかその身に降りかかるであろう罰の存在におびえているのか?――プログラムに選出されるその先日まで、偉そうに見下した態度をとり、ろくに口もきかず、司のことをただそこに“ある”だけの者と認識していた態度が一気に豹変し、こんなへつらえた表情を作り出すようにまでなった辺り実に滑稽で仕方が無い。一応無表情で晴一の横を通り過ぎたが、内心ではあの背中を指差して大笑いしてやりたい気持ちであふれていた。
「おっ、おい、司」
晴一が彼女の肩に手をかけるがすぐさま物凄い勢いで振り払われることとなる。彼女はその薄汚れた声で気安く私の名前を呼ばないで、と逆に拒否の意を視線で示し、何事も無かったかのように大理石が敷き詰められた道を歩き続け、玄関のほうへと向かっていく。その後姿にあっけをとられた晴一は、ぽかんと口をあけるだけしか出来なかった。
「あ、ほんとすみません何から何まで……」
思い出したかのように青沼のほうに向き直り、深々と頭を下げる。プログラムに選ばれたと伝えにきたときの状況と今では衝撃という名の感情は同じといえど、ずいぶん受け取り方が違った。本当に、帰ってきてしまったのだ。今はあの脅威とも取れる血まみれの白い制服を着ていないから視覚的衝撃は避けられたものの、やはりどこか三男の時哉がいつか呟いていたように、亡き母親の姿とそっくりである。母親の化身が帰ってきた。その命を遊び半分に奪った息子たちへの報復のために、帰って来たのだ。
「いえいえ! あ、そういえば、強制転校のくだりですが……」
「あ、えっと……それについてなんですが……家族で一度話し合いまして……」
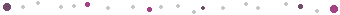
玄関のすぐそばにある階段をあがり、2階にあがる。そこから二手に分かれていて、右に曲がると晴一たち男兄弟の部屋が振り分けられ、左に曲がると司や美津子の部屋があるほうになる。何の疑いもなく司は左に曲がった。一番奥の、日がほとんど当たらない北東の部屋。外はあんなにも暑く汗ばむ陽気なのに、この部屋は心持涼しい。灰色のTシャツを仰いで中に風を送る。ドアを開け、すぐさま閉めた。
正面には机、その隣には本棚。ベッドがあって、コンポがおいてある。それ以外はすべてクローゼットにおさまっているから、ほとんど何もないように見える。司は病院から持ってきた荷物のかばんを開けて、まずは一番上に入っていた我が闘争を取り出した。それを掌にとり、ページをめくる。近所のドイツ留学生、ミハエル・エアハルトに訳してもらったもので、大分古いものとなる。日に焼けて少し黄色くなっているページを何枚かめくった。
この我が闘争の著者であるアドルフ・ヒトラーは、司の尊敬する人物だった。だからこうしてキリスト教における聖書のように、いつも肌身離さず持っていた。ヒトラーは誰が死んでも悲しまなかった。だからあんなに多くのユダヤ人が虐殺されても、後悔など欠片もしなかったのだ。人が蚊を殺すように、ヒトラーはユダヤ人を虐殺してしまった。それが過ちだと語ったのは後世の人間である。
司も、同じ事を所望していた。ユダヤ人――つまり、クラスメートだ――を殺してもなんとも思わず、後悔などしないその強固な精神を。
コン、コン
心臓がはちきれんばかりに警鐘を打った。母親が死んで以来、ドアがノックされた経験など皆無に等しい。幽霊が訪れるのより格段に驚いてしまった。
「司? 俺だけど……」
「入らないで。用があるならそこで言って」
ドアをノックしたのは長兄らしい。晴一はドア越しに妹に話しかけた。その口調はどこかおぼつかないものを感じる。
「その……えっと、プログラムは……不幸だった……な」
今更何を言い出すのかと思えばそんな話で、司は無性にため息が漏れた。我が闘争を丁寧に机の上に置くと、ドアのほうへと近づいていった。姿の見えない兄が、今頃どんな表情をしているのか想像すると実に愉快だ。恐怖に歪んでいるのか、それとも絶望に満ちているのか。
「不幸? 全然そんなこと無いよ」
ニヤリ、と彼女は口の端をゆがめた。それは自嘲の笑みとも取れたかもしれない。彼女は続けた。
「だって、それを不幸って比較して理解できるくらいの幸せなんて、私にはなかったんだから」
「そ……そうか……?」
それ以降会話が続かなくなり、ようやく晴一が墓穴を掘ったと認知したようだ。
「そうだ、あと……強制転校のことなんだけど……お前、宮崎に転校するんだってな?」
「ああ、青沼先生に聞いたの? そうよ、私宮崎の高校に行くことになった。お金だってちゃんと入ってきてるはずでしょ?」
「そのことなんだけどな……俺……いや、俺と、貴正と、時哉はここに残ることになった」
ドア一枚越しでは聞き取りづらい声となった晴一の声をなんとかして聞き取ろうと司は耳をドアに寄せた。
――一緒に宮崎に来ない、どういう事?それじゃ、私の“計画”は――
「真人と洋介は?」
「あいつらはおばさん所に預けることにした」
「何で」
「俺のバイト代だけじゃ生活がままならないからだよ」
「生活保証金があるでしょ?」
「それはお前が使う金だろ」
まぁ優勝した本人が生活保証金を使えなくて、それを勝手に兄弟が使っていたと聞いたら今すぐ殺してやりたいと思うが、それを使わずに、しかも蓮川家が離散と来た。冗談じゃない、と思いながら唇を噛み締めた。
まあいいわ。
「あ、そう。じゃあ勝手にして。まあせいぜい後ろ指さされてさげすめられることね。あの家の娘はクラスメートを15人殺したって」
クラスメートを15人殺した、というところを強調するかのようにはっきりと、そして少し大きな声で言ってやった司は、言い終えた時にはとても清々しい表情をしていた。プログラムでの栄光を認め、腐りきったこの人生に終止符を打った瞬間。そう、プログラムに選ばれた時点で既に蓮川司と言う人間は死んでいるのだ。だからここにいるのはただのモノということになる。
それでいいじゃない、何が悪いの?結局、そうしなければ何もかもがうまくいかないんだから。私は、神になる。今度こそ。誰にも邪魔なんてさせないんだから。
ドア越しに絶句した晴一の顔が安易に想像できる。もうそれから晴一の声が聞こえることは無かった。代わりにスリッパが廊下を這う音だけが吹き抜けに響く。
せいぜい苦しめ。
もがいて、己の罪を呪え。
私からすべてを奪った
そのことを今に後悔させてやる。
Next / Back / Top
