「教えてあげる。誰にも言わなかった……本当のことを」
それを聞いて、夏葉翔悟はニヤリと口元を吊り上げた。
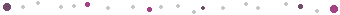
このいたいけな少女だった人間に興味を持ってから早4年以上の歳月がたった。永きを経てようやく分かる彼女の心中は、果たして自分の予想とあっているのだろうかとどこか内心鼓動の音を早くしながら、彼はそのにやけた目で蓮川司を見た。
「週刊誌を読んだなら……もう知ってるわよね。裁判で貴正君が罪を告白した手紙を出されたことを。……そう、私のお母さんはお父さん、それから晴一君、貴正君、時哉君によって殺されたの」
うつむいた調子で神妙に語り始める司を見て、夏葉は少しすまない気分になった。それもそうかと彼は心の中でうなずく。一番信頼していた母親の死を喜んで語る無礼講な娘がどこに居るものか、と。彼はそれ程母親のことを愛していなかったが(ごく一般的な少年だったのだ、小さいころは)、司にとってはそうではなかった。価値観の相違が彼に司の思考を読み取れなくする。
彼女は続けた。
「お母さんは私の、たった一つの生きる希望だった……。お母さんがいたからこそ、私は日陰の生活でも生きて行けた。学校、家……ううん、生きることなんてちっとも楽しくなかったけど、それに全部意味を与えてくれたのがお母さんなの。お母さんはよく私に言ってた。一番でありなさい、すべてを司りなさい。有能でありなさい、高みでありなさい……ってね。私がお父さんに殴られたとき、強くあれってお母さんは言ってた。強くなればお父さんたちも認めてくれる。私はもう、いじめられなくてすむのよ」
そこで一旦言葉を切ると、司ははあ、とため息をついた。すべての記憶がまるで数時間前の出来事だったかのように鮮明に思い出すことが出来るようで、彼女の呟く言葉達もやけにリアルだった。それらすべてが、真実。そうと分かると夏葉は聞き逃さないように耳を傾けた。
「だけど晴一君達やお父さんは私から希望を奪った……。誰もが私の希望を土足で踏みにじった……。もちろん、その後はわかるよね? 私は彼らを恨んだ。もとより大嫌いだったけど、殺したいほど憎んだ。だけど私は弱かった。何もできなかった。父親はかろうじて重傷を負わせたけど、それだけ。私は、とても弱かった……。
だから私は強くなろうとした。自分を変えようとした。髪の毛を染めてみて、まず自分を外見的に変えた。誰も信じないようにした。弟達も、兄も、周りの人間も皆。そんなときよ、プログラムに選ばれたのは」
いつの間にか短くなっていたタバコの火を携帯灰皿にこすり付けてもみ消す。ワックスで立てられた茶髪に手をやると、軽くかいた。
「なるほどね……。無力だった自分を変えようとしてプログラムじゃアドルフ・ヒトラーを名乗ったわけだ」
「別にヒトラーに憧憬を抱いたのはそのときが初めてじゃなかったけどね。私が近所のドイツ人に彼のことを教えてもらったのはもっと前よ。……中学生になったくらいかしら」
そのときもらったのがあの我が闘争の本よ、と付け足して彼女は一旦うつむく。日に焼けて黄ばみ、ところどころぼろぼろになっている和訳本は、感じるところが多々あった彼女にとっては聖書だったらしい。プログラム中においても、おそらくその後の生活においても、身につけていたことは間違いないだろう。
「それが身についてクラスメートをユダヤ人に仕立てて殺し、そんでもって誰が死んでも大丈夫なくらい死に慣れた、って訳か」
「そう。後はわかるでしょ? おかげさまで誰が死んでも悲しくないくらいになって、やっと蓮川家に復讐することができたのよ」
プログラムであれほど感情を壊そうとしていたのは、なるほど余情残さず血の繋がった家族たちを殺す為か――夏葉はタバコをもう一本取り出すと、火もつけずに指の間で転がした。
誰が死んだって悲しくないって……嘘だな、ちょっと――指に挟んだタバコをいじりながら考えてみた。司が優勝を決める前、幼馴染だった新宮響の死にだけは感情的な部分を見せた。しかしあれは彼女にとって悲しいと言う感情だったのかは夏葉には到底理解できない。一般的には悲しかったかもしれないが、司のことだ、何か違う感情があったとしてもおかしくはない。
それでもこうして捕まった罪名は家族殺し。憎き家族と幼馴染では同じ天秤にかける価値もない、という事か。
「ハイ、質問」
しばらく考えたあと、夏葉が小学生のように手を上げて尋ねた。
「何?」
「お前の母親さんを殺した……っていうか死に追いやったのは救急車をすぐに呼ばなかった父親だろ? それからそういう計画を立てた兄貴3人。だったらよぉー、何で他の弟とか兄嫁とか甥っ子とか、とにかく家族全員を殺す必要があったんだ?」
夏葉が取り上げた題材は、どこの週刊誌にも書いてあったが結局答えが出ずに終わったものだった。何せ司の殺人の動機は「家族に対する憎悪」だったため、憎悪の2文字で片付けられてしまったからだ。その成分すらろくに調べずに。夏葉が気になっていたのはどういった憎悪で、どんな由縁のある憎悪か、だった。
司はにやりと笑っていた表情にヒビを入れて少し口元を下げると、しばらく黙った後にまた口を開いた。
「蓮川の家ではね……代々女の人が虐げられる生活が続いてたのよ……。私のおばあちゃんはそれ程じゃなかったんだけどね……。そういう家庭が、この世にひとつでもあっていいと思う? 私はそう思わない。“私みたいな人間”をもうこれ以上作らないためにも、これは“見せしめの殺人”にする必要があった。蓮川家がどれだけ悪の巣窟かって言うのを、全国に流布する必要があった。
母親を殺された復讐の矛先は、“そういう環境”を作った蓮川家を根本的に叩ききるところからはじめたのよ」
「だからってなんも関係ない弟とか兄嫁も――」
「真人や洋介は」
夏葉の言葉をさえぎって、司は声を荒げた。
「私が血まみれの制服で卒業式に出た次の日から集団でイジメにあっていた。だから叔母さんに預けられたのよ。逃げるためにね。プログラム優勝したっていう血縁関係者がいるだけで将来は絶望的になるなら、なおさら殺人者の姉がいますなんて言えないでしょ? 特に、蓮川なんて珍しい苗字なら隠せるはずもないわ。
私は親切で、殺したのよ。本当は、殺したくなんて……なか……った……けどね、うん。でも、こればかりはどうしようもない。
もし真人と洋介が叔母さんに完全な養子として引き取られたならきっと運命は違ったかもしれない。別の苗字になるからね。でも彼らはそうしなかった。蓮川であることを受け入れた。こんなことになるなんて、夢にも思わなかったでしょうね。私が銃口を向けたとき、2人ともすごい顔してたし。
もし……もしもの話、私が真人たちを殺さなかったら、きっと私のことを恨むに違いない。大人になってから、また同じように女性を信じないで虐げる大人になるかもしれない。そうすれば私と同じような人間が出来上がる。それだけは、それだけはどうにか食い止めなきゃならないって……。真人たちに限ってそんなことはないと思ったけど、不安要素は全部摘み取らなきゃ気が済まなかった」
夏葉はもう何も言わなかった。水が流れるようにごく自然に司の主張を受け入れ、肯定も否定もせず、ただ聞き入れていた。司を連れてきた看守が背後でカリカリと鉛筆を走らせているのが見える。これらは記録され、きっと看守長のほうへと渡されるだろう。それでも今更下された死刑判決がこの証言によって翻されることはきっとない。何より彼女がそれを望んでいないだろうと夏葉は考えた。それならむやみに『外にバレるぞ』と言って彼女の真実に歯止めをかけるという野暮なことはせず、何も言わずただじっと聞いていればいいと思った。
「そういうことはね、憎しみと同じよ。憎しみの連鎖はどこまでも続く。だけどね、先生。憎しみの連鎖はひとつだけ断ち切る方法があるのよ。何だと思う? ……ふふっ、みーんな殺しちゃえばいいのよ」
彼女は手錠をかけられた両手を高く掲げて天井を見上げた。実に愉快だと言わんばかりに爽やかに笑い、まるで天井の代わりに澄み切った青空がそこにあるかのように晴れやかな顔をして。
「兄嫁の夏樹って人いたでしょ? 私、彼女に情報たくさんもらっちゃった。ちょっとね、商談を持ちかけたのよ。蓮川家の財産を全て譲る、ってね。結構使えたわ。どうせ彼女も蓮川の財産目当てで晴一君に近づいたんだし。使えるでしょ? 証拠隠滅ついでに殺してやったわ。私が犯行を行った日に兄弟達が全部あの家に集まることを教えてくれたのも、彼女。
ホントいいタイミングだったわぁー。さっき、先生が推理したでしょ? 20歳になれば犯罪者は実名公表。あれ、正解。そうよ、犯人が一族の中にいることを見せしめないとどうしようもないからね。血縁内で殺人なんて、いかにもおぞましい惨劇だもの。それを民衆に知らし召すためには私の名前が必要……だから4年間も待ち続けたのよ。それでなきゃすぐにでも殺しにいってるからね。
私、毎日お母さんに誓ったわ。絶対に、殺す、と」
空を仰いでいた顔が急に夏葉のほうに向くものだから、彼は驚いてかしこまった。緩やかにカーブを描いた彼女の眼から見える瞳の奥、またあの殺気――プログラム中に灯っていた殺意――が舞い戻ってきたように見えたからだ。
「私が杜撰な犯行現場を残して完全犯罪に程遠いものに仕立て上げたのも、全部捕まるため。逮捕される時期はできれば週刊誌とかが話題にくっつかなくなったくらいが一番いいわ。逮捕されたらまた話題が浮上するでしょう? そうしてより長く長く蓮川の醜態をさらして滅んでいく姿を、私は高みから見下すの。
これらはね、全部計算尽された計画なのよ」
彼女の話が一旦途切れた。司は今も微笑んでいた。後悔の欠片もない、そんな無垢な表情を浮かべて。
要するに、とにかく最低最悪な方法で家族を殺し、最低最悪な方法でメディアを媒体にしてそれを多くの人に知らしめしたいという事だ。
それが彼女の復讐。母親と自分の自由と理想と希望を土足で踏みにじった、等価的な罰。
「……それ、全部中3のときから考えてたのか?」
もう一度椅子に座りなおし、透明な仕切りの向こうにいる殺人犯を正面に見据えて、夏葉は質問した。今までの話をすべて聞いていると、本当に起きた話なのに現実離れしているように思える。当初想像していた家庭環境よりも、実際は更に複雑でもっと入り組んでいて、自分を虐げた家族への憎悪なんて言葉ではとてもとても言いくるめられないような気がした。
それは、果たしていつからそんなことを考えていた?浮かび上がった疑問を夏葉は素直に尋ねた。
「大体の輪郭が形成されたのは、お母さんの葬式のとき、晴一君たちがお母さんを殺したことを聴いた次の日からかしらね。言ったと思うけどそのときはすぐにでも殺してやりたかったけど私はお父さんの殺人未遂で少年院に入っちゃったし、出所して以降もあまりにも弱くて実行できなかった。まあ、20歳以上になって名前を公表できるようになったら、すぐに殺しにいってやろうとは後から考え付いてたけど。
でも20歳になる前にまさか家族が分散するなんて夢にも思わなかった。てっきりプログラムのあとは一緒に宮崎に引っ越すのかと思ってた。私から逃げようとしたのよ、手間のかけさせる意地の悪い奴らだからね。
計画の詳しいことを決定したのはプログラム優勝したあとだわぁ。プログラムで銃の使い方とかもわかったし、後は綿密な計画を練って時期を待つだけだった。家族が分散してしまう以外、すべてが私の計画通りだった」
火のついていないタバコを指先でいじりつつ、彼は司の顔を凝視した。と思うと彼はいきなりふっと笑い出し、肩を小刻みに上下させて笑いを堪えた。
「何? 可笑しいところでも?」
癪に障ったところがあったのか、司は声にドスをかけて問いただした。
「いやあ、別に何でもねえよ。ただ……死刑にするには惜しい人材だなぁ、って。世の中がびっくりしてるぜ? お前みたいなのがまだ20そこそこのガキだって言うんだからな」
それを聞くと、普通の笑いではなく、憐れみをかけられた笑いのような気がしてならない。司は口をへの字に曲げた。
「……せいぜい褒め言葉として受け取っておくわ」
ため息交じりに苦言を吐いた。
「おやおや、ずいぶんさばさばした性格になったんじゃないか?」
「独房だと奇襲がないから安心して暮らせるからよ。心が広くなったんじゃない?」
「そんなのんきに暮らしてる間も、世間じゃお前の批評ばっかり垂れ流しだぜ」
「言いたい奴には言わせておけば? だって、誰一人真実を知らないでしょ? 私からしたらくだらない妄想にしか過ぎない。まぁ結果的にはそんな批評も役に立つわ。やっぱり惨殺事件の犯人が身内で、しかもプログラム優勝者だったら、メディアは勝手に私がどんな屈辱を受けてどんな仕打ちを受けて育ってきたか全国的に流布してくれるでしょ? そうすれば蓮川が衰退することが著しいって手に取るように分かるわ。先生の言う通りって訳よ」
最後にこれがすべてだといわんばかりににやっと笑うと、彼女の言葉は終わった。
相変わらず使用武器の入手経路については自然に消されていたが、今の夏葉にとっては重大なことではなかった。むしろ、司のその堂々とした立ち振る舞いに唖然としていた。
「他の死刑囚みたいに気が触れないんだな」
畏敬の念をこめてそう言った。死刑囚に関する資料や本では、誰もが絶望し、時には狂乱してしまうことすらあると書いてあったが、目の前にいる死刑囚はどの資料にも書いてなかったパターンに当てはまる。毎朝、1人の刑務間が死刑囚の独房の前を歩く。死刑執行の日はその刑務間に扉を叩かれるのだ。誰もがたった一言、絶望の言葉を浴びせられる危険性を憂い日々過ごしている。たった一言、死刑執行だ、という言葉を。したがっていつ呼び出されるかわからない死を前にしても、こうして胸すら張れるほど堂々としているのは幾分珍しいパターンではないだろうか。
「当たり前でしょ? 私は一度プログラムっていう死地を越えてるのよ。これくらいどうって事ないわ。お母さんっていう味方のために、敵を殺した。それの何が悪いの? それが罪に問われるなら喜んで甘受してやるわ」
そう考えると、彼女の言葉一つ一つはどこか開き直っているようにも見えた。
「そうだよな、なんたって、お前は神だもんな」
嫌味程度で軽く言ったつもりなのだが、司の表情が一変したので夏葉が逆に驚かされた。しかし司はすぐに驚愕の表情からいつもどおりの無表情に戻り、それから少し微笑んだ顔にぎこちなく移行させると、「神だったのは、私が蓮川家の人間を全員殺したあのときまでよ」と答えた。
「あのあと捕まって、法廷に出されて、死刑判決もらって、少し考えたの」ずいぶん途切れ途切れに痛ましく話す。
「私は、化け物なの? 神なの? ……って。ねえ夏葉先生、先生はどっちだと思う?」
椅子から身を乗り出して尋ねてくる彼女の姿を見て夏葉はたじろいだ。畳み掛けるようにして「凡人は天才になれないように、化け物は神になれないのかしら?」と尋ねてくる。追随は許されなかった。
結局夏葉はうまい答えが見当たらず、もごもごと言葉をにごらせたままその場は沈黙で終わった。
この痛々しい沈黙を打破しようと、夏葉は別の話題を提示した。
「司法による、自殺か?」
罪を罪と認めていないような言動を胸を張ってはっきりというものだから、勢いあまって夏葉も思っていたことを躊躇なく吐き出してしまった。饒舌なほどにすらすらと口車の止まらない司を前にすれば、今まで聞けなかったことはすべて今のうちに聞いておかなければ損してしまうと考えるのはごく自然であるが。
そう、今しか聞けない。少なくとも、もしかしたら明日死刑になるかもしれない人間を目の前にしているのだ。苦労して面会までこじつけたのだから、このチャンスは逃せない。別の話題を盛り上げようとしていた彼のことだから、この話に無条件で熱を入れた。
「かの有名な、お前の尊敬するヒトラーは第三帝国の建国にすべての人間が反対していることに気付いて、未来に絶望し、自殺した。お前もまたヒトラーの名を語るなら、最期は潔く死のうとでも思った、のか?」
――1945年4月30日、敵軍の首都侵攻、下降していく戦況、燃え堕ちる未来を見据えて、先がないことを知ったヒトラーは、ピストル自殺をした。例え本当は神であろうが化け物であろうが、彼女がヒトラーのようになりたいと願ったのだったら、ヒトラーのようになりたいと切実に望んだのだったら、その最期が等しく同じ方法でもなんら違和感はない。尊敬する人の死に方まで真似る方法は、死に場所を見つけられない不器用な蓮川司だからこそ出来る死に方なのかもしれない――夏葉はそう考えた。
「……先生、結構勘鋭いのね。何でもお見通しなのかしら?」
いきなりの話題転換にも不愉快感を見せることなく、素直に驚く彼女は自嘲気味に声をあげて笑った。それを聞いて夏葉の予想は確信に至る。
やはりこの不器用な女は、法によって死に場所を与えてもらおうとしたのだ。
「……そうよ、私は最後には法によって殺されようとした。先生の言うような、法による自殺。それが死刑ね。伊達に生半可な気持ちで人を殺したわけじゃない。私にだって、私なりのケジメの付け方って奴があるのよ」
彼女は、微笑んだ。
「それに、私の存在理由は蓮川への復讐……それ以外の何ものでもないわ。そうやって5年間、それだけのために生きてきた。それが終わった今、だらだら生活するならさっさと死んだほうがいいと思ってね。もう、この世に居る意味すらないもの。私には、もう何も残ってない」
実にすっきりとした笑顔だった。彼女のいうところ、もう何も残っていない。まっさらになった彼女はこんなにも奇麗だったのか、と彼は目を見張った。灰色がかって肩まで切られた髪の毛も、ほっそりしすぎて血行の悪い顔も、ガリガリにやせ細って囚人服が似合わないその体躯も、急に全てが麗しく見えた。なぜだろうか。
「戦争は、終わったの」
司は最後にそう一言付け加えた。彼女の存在理由をかけた戦争――理想郷の形成のための戦争。しかし、邪魔者がいない理想郷など、やはりただの独裁国でしかないのではないだろうか?それは幼稚園時代、ブロックで作った自分だけのお城と似ている。
「すざましい、生き方だったな」
そんな彼女に、彼は声をかけた。彼女がやけに麗しく見える驚きもあったが、4分の1ぐらいは哀れみもあった。それでも必死になって21まで生きて、そうして自己の存在理由を完結させた彼女に哀れみなどいらないだろうと思いついて、4分の1を100分の1に減らした。残りの穴埋めは、ひとりの大人として、未熟に育ったその精神力を撫でてやった。
本当に奇麗な人は、意志の強い人なのかもしれない。そんな幻覚でさえ目の前をちらつく。
「本当に。……短い人生だったけどね」
そんなことを呟きながら少し困ったような悲しげな表情を浮かべて夏葉を見上げた。
「俺、今度ガキが出来たら司って名前にしようかな」
「やめとけば? 私の生まれ変わりみたいで私が嫌だから」
「ハハッ、そうだな」
ちょうどそのとき、司と一緒に入ってきた看守が『面会時間が終了します』と口を挟んだので、会話が途切れた。司は椅子から立ち上がり、夏葉に向かって一礼をする。染めた髪の毛は伸びきって切られたために元の灰色がかった髪の毛に色は戻り、肩ぐらいの長さに切られている。灰色の囚人服を身にまとい、やせた体躯は年年歳歳を感じさせた。――あれ、さっきはあんなに奇麗に見えたのに。
彼女がくるりと身を翻して、ようやくタバコに火をつけ始めた夏葉を凝視した。
「先生……私、先生に全部話したら、何か本当に何もなくなっちゃった気がした」
「ああ? ……いいんじゃねえの? “旅”をする時にゃ、身軽なほうがいい」
「……皮肉ね。たどり着く場所もない旅だって事?」
彼女は一旦扉の向こうへと足を踏み出したが、思うところがあったのかすぐ振り向いて最後に夏葉のほうをみた。
「先生、今更思うことがひとつだけあった」
「何だ? 言ってみろ」
「……生まれながらに迫害されて……私こそ、ユダヤ人だったのかもしれない」
一瞬拍子抜けした表情で夏葉は火のついたタバコを加えたまま彼女を見たが、すぐに我に返り、返答した。
「ハッ……笑えねえ冗談だぜ。本当に迫害したかったのは、自分自身だってことか?」
冗談のつもりで言ったのだが、彼女はニコリともせずに、うつむき加減で少し悲しそうな表情をしてこう返してきた。
「……そうね。そうかもしれない……」
それはさしずめ、迫害されたユダヤ人の哀れな一人相撲か。
開かれたドアから光を浴び、後光にその身を照らしながら彼女はただ一言、肯定の言葉を述べた。うつむき気味のその姿は、次第に扉に吸い込まれて消えてく。バタン、という音を最後に、もう二度と夏葉が司の後姿を見ることはなかった。
「クソガキが……。寂しい背中見せて消えるんじゃねえよ……」
タバコの煙をめいいっぱい肺に入れ、長くゆっくりと吐き出す。口からタバコを話すとしたうちをしてからもう一度タバコをくわえた。
だれも居ない面会室に、夏葉の舌打ちだけがむなしく響いていた。
あの法廷にいた誰かが、後にこう証言した。
判決が下されたとき、確かに彼女は少し上を見てにこりと笑ったのだ。
笑ったのだ、『死刑』という言葉を聞いて。
Next / Back / Top
