あの法廷にいた誰かが、後にこう証言した。
判決が下されたとき、確かに彼女は少し上を見てにこりと笑ったのだ。
笑ったのだ、『その言葉』を聞いて。
「判決を下す。被告人蓮川司は強盗殺人罪及び住居不法侵入罪、特別銃刀法違反で――死刑に処す」
これが第一審2回目においての、裁判所の判決だった。
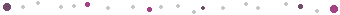
死刑が宣告された10月の第一審・2回目から半年。
スピード結審で事件発生から約1年足らずで被告人蓮川司の運命は決まった。
死刑判決。
宣告されたものは極刑だった。
刑が決まったので今までいた拘置所から刑務所の死刑独房に追いやられた。四畳半に加え便座がある程度の狭い部屋。そこで司は13階段を上る練習をするのだ。いつの間にか伸びた髪の毛は小学生のときのように薄い灰色に戻り、目からはいつの間にか殺気が削がれて、判決を受けていた頃と比べるとまるで別人のように変わっていた。
毎日本を読んでは時間を潰していた。プログラム後に入った高校は1年で中退したので勉学はほとんど身についていない。辞書を用いて英語の長文を読んだりしたこともあった。
冬もあけて春の陽気が清々しい4月のある日、誰にも触れられることがないと思っていたはずの扉からノック音が聞こえてきた。次に扉が開かれ、その向こうに立っていた刑務官は無表情のまま「死刑囚833号、面会だ」と言ってから部屋に入ってくる。
「面会?」自由だった両手に手錠をかける刑務官を訝しげに睨みながら司は尋ねた。しかし刑務官の彼はそれ以上答えず、カシャンと手錠がはまる音だけが無為に響いた。
牢屋の扉をくぐり、無機質な廊下に出る。入所以来半年ぶりに見たそのグレーベースの廊下は今日もひやりとした冷気を吐き出していた。久し振りに長く歩いたからか、足取りがかなり不安定でおぼつかない。もともと体力は人並み程度についていたはずだったが(でなければ、銃をそう簡単に操れない)、ここ数年間ほとんど動いていなかったので動きに違和感を感じる。しかしそれよりも面会など、死刑判決を受けてから一度もしたことがなかったものに今更誰が来るのだろうか考えるほうが先決だった。
それから歩いて少し、面会室にたどり着いた。部屋にはいるとほぼ中央に透明なプラスチック製の仕切があり、その向こうに面会人はいた。
「よぉ死刑囚第833号。どうだぁ? 刑務所の居心地は」
仕切の向こうの椅子にだらし無く座り、足を投げ出していたのは懐かしい顔の夏葉翔悟だった。彼女の中学3年生の時の担任であり、なおかつプログラム担当教官でもあった彼は、今でも相変わらず髪の毛を薄い茶色に染めて目の下に睡眠不足によるクマを作り、卑しくニヤリと微笑するのを常としていた。彼は足を組みなおすと、プラスチックのしきりにあけられた小さな穴のほうに向かってわざとらしくタバコの煙を噴き出し、それから携帯灰皿にタバコを押し付けて火をもみ消した。司にとっては教師であり人生の先輩でもあるはずの夏葉を、彼女はあきれた目で見つめ、ため息と共に正面の椅子に座った。こうして2人が対峙して座るのはプログラム優勝後以来であるのをふと思い出す。
はじめは面会人が夏葉であるという意外性に驚いたような表情を浮かべしばらく唖然としていたが、次第に正気を取り戻して、失くしかけていた話す機能をフル回転させて言葉を続けた。
「まあまあね……名前が番号になった今じゃ、せいぜい罪名が肩書きって所かしら? それに、三食保証、冷暖房完備、ありとあらゆる時間が確保されてるここじゃ、読みたい本も色々読めるしね。悪くないわ、独房暮らしも」
「ふん、ずいぶん大層なもんだな、犯罪者になった気分って奴はよ」
皮肉そうに啖呵を切るが、実際は微笑さえ浮かべていた。夏葉から見える司の姿――悪くはないという独房暮らしを堪能していたようだが、明らかにやせ細り、とても20歳とは思えない老けた姿。あの煌々とさえしていた殺意や生命感は、やはり復讐という名の添え木があってこそ存在したのだろうかとさえ考えさせられてしまう。添え木を失った今では、痩せて朽ち果てたただの木のようだ。
「確か法律では死刑囚の面会は家族と教誨師と弁護士しか認められていないはずだけど?」
人と話すことが久し振りすぎてうずうずするのか、司は従来では考えられないほどの饒舌ぶりで質問を繰り出した。
「そこのリストにな、特別に認められた人間も付け加えとけよ。俺はその特別に認められた人間ってわ・け。分かる?」
「そう、相変わらず汚い人生送ってるのね。いくら積んだの?」
「うるせーガキんちょ!! 俺がここに来るのにどんなに苦労したか分かってないだろォォ!! 払ったのは俺のここまでの電車賃だ!!」
透明な仕切り越しに夏葉はつばを吐かんばかりに大声を上げた。実際、そう嘆くほど苦労した彼である。
まず『蓮川に面会がしたい』と弁護士に食って掛かったが法律の関係上の問題があるとなかなか相手にしてもらえず、国家公務員の権力を使ってみたがやはり司法の前にはひれ伏してしまい、そしてようやく脅しまがいで面会にまでこじつけたのだ。一般人が死刑囚に面会したがるほうがおかしい、と何度も不審に思われたが、そこは司とは無関係の人間ではないという事でカバーした。法律関係には無知もいいところだったので、大学時代にもっと広範囲を勉強しておけばよかったと何度後悔したことか。
そういったいきさつを事細かに説明してもらって、ようやく司は納得したかのように一度だけ首を縦に振った。今まで見せていた怪訝な表情を一転させ、にわかに微笑みだした彼女は、この瞬間に人が変わったかのように話し出した。
「本当に久し振りね、先生。何年ぶり? 5年くらいになるかしら。まだ死んでないみたいだから担当教官の仕事を続けてるの?」
目を細めてニコリと笑いながらそうたずねた。その声がやわらかかったのは、やはり懐かしい人に出会えたためか。もう二度と刑務官以外の人間に会わないと思っていた司を驚かせたあまり、本音が零れ落ちたようだ。
「ざーんねん。今はちゃんと教員免許取り直して普通に先生やってる。まぁ、担当教官のほうは資格保留ってことで、やばくなったらそっちに戻るつもりだけどな。まあ公務員はクビとは無縁だからねえ」
「へえ? それじゃあ担当教官って、派遣会社みたいな感じなの?」
「それとはまた違うけど……まあ、俺の権力があってこそ出来る高等技術って奴?」
「初耳ね。先生に権力なんてあったの。仕事クビになって社会の底辺でへーこら言ってるかと思ったけど」
「……てめえクソガキ……ひっぱたくぞコラ」
司のいやみに、夏葉は眉をひそめた。それだけ流暢に人のことを馬鹿にできるなら、惨殺犯も捨てたもんじゃないなと内心思ってしまう。透明な仕切りの向こうにいる人間は、殺人犯とは思えないような笑顔を浮かべて、ぺらぺらと口を動かした。
「で? 何しに来たの」
手を前で手錠で縛られているためか、当たり前だが自由な行動はかなり制限されている。それでも規律正しくぴんと背筋を伸ばして椅子に座っていた。もはや手錠で動きを制限されていなくても、それがごく普通のように微動だにしなかったろう。
「んだよ、俺が来たらそんなに嫌か?」
「別に。ただ、先生の顔見るとね、やっぱ思い出しちゃうのよね……プログラムのこと」
プログラム、その言葉を小さく呟くと彼女は下を向いた。
「ほぉー? お前はそんな弱い人間だったのか。知らなかったぜ! 世を騒がせた犯罪史上最悪の惨殺鬼がよぉ、そんな弱い人間だったとはな!」
ここぞといわんばかりに夏葉は声を大きくし、胸を張って嫌味を返した。司は上目遣い気味に夏葉を睨むと、少し不機嫌気味に「……前言撤回。好きなときに来るといいわ」と切り替えした。
「冗談だよ。好き好んで誰がこんなとこ二度も来るかよ。今日来た理由はねー、こーれ」
肩をすくめつつ言い返すと、夏葉は足元においてあったのだろうバッグから、ひとつの封筒を取り出した。白い封筒に、薄水色の便箋が収められている。その便箋を取りながら「これ、あとで差し入れとしてお前にやるから」と付け加えた。
「何? それ」
「お前んちのポストに入ってた手紙。悪いけど先に見させてもらったぜ?」
既に封が開けられていた封筒から手紙を取り出し、仕切りのところに貼り付けて読むように催促した。
あなたには生きる権利は毛頭ございません。
一度死ぬことをお勧めします。
そうつづられた手紙の最後には、「新宮日名子」と署名が付け加えられていた。新宮、そんな懐かしい苗字を思い出して、一瞬にして新宮響のことをその名前とかぶらせた。
響のお母さん――家の居心地が悪いとき、隣の家の新宮家にいつも逃げ込んでいた司を温かく迎えてくれた彼女。響と母子家庭のためか、女の子の司をまるで本当の娘のように可愛がっていた。同様に響のこともものすごく可愛がっていた。だから響の母親がこんな平坦な文字の羅列に憎悪を込めたくなる気持ちもわからなくなかった。
「……これ、いつのもの?」
手紙から視線をはずし、手紙をしきりに貼り付けて司にみせていた夏葉を見た。
「俺がこれ見つけたのは……あの家に誰もいなくなったくらいからか? 投函されたのはいつか知らねえけどな」
司は今まで保ち続けていた整った姿勢を初めて崩し、背中を椅子の背もたれにかけると、深々と椅子に座りなおした。
「まったく……そういうのはもっと早く持って来るべきなのよ。時間が経つにつれて罪の意識は薄れていくものだけど? ……第一、私はプログラムで人を殺したことを罪とは思ってない。だって、プログラムで人を殺しても殺人罪にはならないって言ったの、紛れも無く先生じゃない?」
「まあ、そりゃぁそうだけどよ。この手紙見てなんともおもわねーのか? それにプログラムのこと思い出すと胸が詰まるだろ?」
「お生憎様。そういう感情はもう何も残ってないの。さっきのは撤回したはずよ?」
本当に別人のような饒舌ぶりに舌を巻きながらも「けっ、かわいくねーなー」と吐き捨て、手紙を元の封筒に戻した。
感情の欠落か?
夏葉は目の前にいる死刑囚を凝視した。彼女は以前、人を殺して自分の中の理性を殺した、と言っていた。その割にはプログラムの最後では弱音すら吐き、わずかに残されていた人間味を垣間見せた。それが今ではどうだろうか。コンクリートの城に閉じ込められたラプンツェルが髪の毛を垂らして助けを求めたが誰にも相手をされず、挙句の果てに発狂したような成れ果てになっているではないか。
捨てたのは何か。感情か、理性か。それとも人間か。もしくはすべてか。
しかし懐かしい顔を前にして嬉々として語る司を見て、夏葉は心の中で首を横に振った。子供だった。
「もう一度聞いていいか。お前にとってのプログラムは……一体なんだったんだよ」
「だから言ったでしょ? 先生のいうところ、感情を壊すためのところ。ああ、クラスメートはどう思うって話? ……そうね、ユダヤ人、排除すべきものよ……ね」
やはり欠落していたのは感情かもしれない。淡々と起伏のない言葉で彼女は夏葉の質問に返答した。
夏葉は大きくため息をついて、頭を抱えながらこう言った。
「理性とか感情とか、そういうもんなくしたがるから、プログラムで皆に化け物って言われるんだよ。それらどっちも生き物だから揃ってるもんだろ?今の時代、化け物でさえ理性ぐらい持ってるよ」
「私がプログラム中に化け物呼ばわりされてたの、何で知ってるの?」
いきなり質問されて驚いた夏葉は「えっ?! いや、その、ほら……お前プログラム終わった後に言ってただろ?」と苦し紛れに答えた。プログラム中に生徒の首輪に盗聴器を仕掛けてあることは内密になっていて、それを司は知らないことをすっかり忘れていた。
「そうだったかしら……覚えてないわ」
司は首をかしげた。
国家秘密に相当する(何せ盗聴はプログラムにおいてかなり重要なものだから)秘密をこれ以上追求されないように、改めて椅子にだらしなく座り、次の話題へと映った。
「んじゃよ、次。俺さあ、ずっと聞きたかったんだよな……お前の口から、ホントのことを」
「ホントの事?」訝しげに聞き返した。
「ああ! 大丈夫。俺、お前の弁護士にきつく言われてるから、お前に絶対に生きる希望とか与えないから。つーか与えらんない」
「……大丈夫。私も先生の口から希望をかけられるような言葉が出るなんて絶対に信じてないから」
「……減らず口め。まあいいだろ。じゃ、手っ取り早く最初の質問。お前、兄貴に母親殺されたんだろ? 週刊誌で読んだぜ。裁判で手紙が証拠として発表された、みたいな。お前の家族、お前と母ちゃんに辛く当たったんだってェ? お前の味方が母親だけだったとも書いてあったな。だったらそんな大切な人間殺した兄貴たちのこと殺したくなるよなぁ、その気持ちはわかるぜ。でもよ、どうしてプログラムのあとにすぐやらなかったんだ?」
急に目のともし火を吹き消したかのように昏くなった。それはプログラム終了後と同じ、まるで何ものも写らない暗闇のような漆黒のガラス玉。切れ長の目が動物的にぎょろりと動いて夏葉を睨む。
「疑問に思ったことは先生だけじゃないわ。弁護士も検事も警察も、皆そうやって聞いた」
「そう、お前は聞かれたことは流暢に全部答えた。あんなに寡黙で人付き合いが悪かったお前が、だ。だけどどの記事見てもこれについて詳しく書いてる記事がなかった。ってことはお前がちゃんと話してないか記者にもどっかでストップがかかってるってことだろ? あー、待て待て。言うなよ? 俺が予想したこと聞いて欲しいんだよ」
長い話になりそうだった。夏葉はジッポーのふたを開け閉めしながら司を凝視する。カシャン、カシャン、という無為な音と夏葉の声が混ざり合って狭い面会室にこだました。
「まず第一に、お前には武器がなかった。プログラム中だと無料配布だからな、武器は。だけど現実に出りゃァ裏で手まわすしか武器が手に入らないってもんだよなぁ。犯行に使われたサバイバルナイフとか、家においてあった刀はまだしも、外国製の拳銃使っちゃ密輸に疑惑も出るってもんだ。そう簡単に手に入るかよって話で」
犯行に使用された凶器については、司は法廷でも取調べでも不思議なくらい何一つ証言していない。誰も彼もがそこが怪しいと突いていたが、夏葉も同じことを思っていた。しかしいまだ捜査は難航、司も何も言わないので密輸ルートが洗い出せないでいた。彼はとにかく、司が犯行を起こしたときからずっと暖めてきた予想を繰り広げてみた。夏葉の予想はまだ続く。
「ハイ次、第二。こっちはかなり自信ないけどよ……。この国では20歳になると青年って認められて事件を起こせば名前が出されるんだよな。少女Aじゃ済まなくなる。ただでさえ複雑な家庭で、しかもよりによって母親が死んだ原因が兄貴達にある、そんな最低な家族……蓮川家。それが世間にばら撒かれたらどうよ? つまりな、お前が家族全員を殺したのは、母親を奪った復讐であって、そんな環境にあった蓮川って言う家柄を世間様にバラして根元からたたっきる目的があったからじゃないのか? だから……20歳になってから名前を出して、より蓮川家のすべてを流布して……そうすれば、蓮川って名前の人間は自動的に界隈から淘汰される。かの有名なアドルフ・ヒトラーの親戚が、戦争のあと民衆から拒絶されたようにな。お前、誕生日5月中旬だろ?犯行が行われたのは5月下旬だ。まあ、そのあたりは偶然かもしれないけどな」
長い語り口もそこで一旦途切れた。アドルフ・ヒトラー、司を語るにおいて重要なキーワードとなるその言葉は、既に週刊誌上に上げられている。誰が話したのか知らないが、プログラム中の司の行動がすべて民衆に知られているのだ。ユダヤ人廃絶をめざした独裁者を気取る、大量殺人者として。そのキーワードを話の中に入れて一旦夏葉は姿勢を変えた。
「どうよ? 100点満点中……何点?」司にそう尋ねた。
「そうね、98点くらい?」
やけにあっさり高得点をつけた司の表情は、嘲笑に満ちていた。あと2点分、その2点が司の行動に関して最も欠けてはいけない要素なのだが、それはただ単に司の気持ちのものであって、誰にも話したことないのだからしたがって司以外の誰一人、知るはずもなかった。
「お前の殺人計画は完全犯罪には程遠いよな。あれほど惨殺しときながら、まるで捕まえてくれって言わんばかりに証拠が出揃ってたみたいだぜ?」
あと2点を何とか確保しようと、夏葉はもう一段階詰めてみた。しかし嘲笑は変わらずその色白の能面の上に乗せられている。その自信たっぷりの表情を見て逆にあきれ返り、ため息と共に手を軽く上げた。
「……ギブアップ。もしよかったら教えろよ。あと2点、何が足りない? お前、ホントは
ついに嘲笑の能面は破れ、にんまりと歪んだ口の端からふふっという笑いにも似た吐息が漏れた。
「大体は先生の予想と合ってるわ。だけどあと2点分大切なものが無い。これが聞きたかったんでしょ? 私の口から語られる、本当の真実って奴」
「教えてあげる。誰にも言わなかった……本当のことを」
Next / Back / Top
