「お願いだからこの怪我早く治して、私を卒業式に出して!!」
礼服のような白さを持っていたはずの制服を紅に染めた少女は、そう悲痛に歪みながら叫んだ。
とにかく左肩の銃創は女医により一旦応急処置を施され、モルヒネの麻酔の後、すぐさまとある市にある国営病院へと搬送され手術を受けることとなった。
3時間近くの手術の後、少女は死んだように眠りについた。
それはまるで、ほぼ同時刻、エリア28内で回収された検死死体と同じように。
ピクリとも動かずに、息を潜めて。
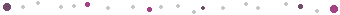
1999年3月15日朝。太陽が住宅街で構成されている地平線からすっかり顔を出した。40度ほどに傾いた太陽が先日まで降っていた雨を忘れたように輝いている。それとほとんど同時に国営病院から一台の黒塗りの車が出てきた。プログラム終了後、蓮川司が収容されたあの病院からだ。
「いいんすかァ? 仮にも手術明けの病人を連れ出したりして! オレ知りませんよ!」
開いた窓が閉められてゆくとき、そんな声が漏れた。若々しいその声は、1998年度第50号プログラムの副担当教官を務めていた青沼聖のものだ。彼は車の後部座席――それも向き合った形に並んでいる座席――に座っていて、同じく後部座席の向かい側に座っている夏葉翔悟と司に向かってたずねる。
「いいんだよ。その仮にも術明けの人間がどーぉしても卒業式に行きたいっていうから全部許されんの! 責任はぜぇーんぶこいつなの!」
約2日間ぶりにプログラム担当教官の任をとかれた夏葉は、予備が切れていた煙草をごっそり買えて上機嫌らしく、厭味を言われている割にはにこやかに笑いながら足を組み、蓮川司を指差した。マイルド系のタバコのにおいが車内に充満した。
「でも蓮川さんは怪我してたんすよ?! しかも左肩の肩甲骨が複雑骨折! どんなに頑張ったってあとしばらくは絶対安静っすからね。それを止めないのは大人としてプログラム担当教官としてどうかと思うっす! ねえ蓮川さん?」
青沼は語尾を上げて軽く尋ねるが、司は平然とした表情で座り続けていた。例の左肩には包帯が何重にも巻かれた上であの薄汚れたワイシャツを着ているので、外見的には違和感がある。
「……薬のせいかしらね、痛みは全然無い。ちょっと動かしづらいけど、何とかなるでしょ」
どうやら青沼の質問には興味も示さなかったらしい。
プログラム中に受けた唯一の負傷で、肩の肩甲骨複雑骨折。他にもその近辺の筋肉が断絶していたのでそれをつなげる手術をした。そのうえこの1日半の間に体験したことが負荷となり、元々ほっそりしていた頬も肉がいっそう削がれているように思えた。その不釣り合いな状況には笑うしかない。それに術後の割には病人用の寝巻きではなく、しっかりと血に汚れて汚くなったあの制服を着用している辺り、何か意図があるのだろうか。
車は高原第五中学校へと向かって走っていった。この病院から大体40分かからないで着く距離だ。
なぜ今頃こんなに急いで体育館へ向かうのか、それは司の強い希望からだった。プログラム終わって早々彼女が吐いた第一声が「お願いだからこの怪我早く治して、私を卒業式に出して!!」。その後血を流しすぎたのか、がくりと倒れると気を失った。あっけにとられたのはむしろ本部の置かれている分校にいた夏葉と青沼のほうだった。――なぜそこまで急ぐ必要があるのだろうか。しかしそれにしても何のために卒業式に?――担架に乗せられ、応急処置のため医務室に運ばれていく彼女の姿を見て、彼らは共通の思いを抱いた。
そして司の手術も終わり、なぜそんなことを望んだのか聞くタイミングも逃して今に至る。実を言えば聞こうと思えばいつでも聞けたのだが、何も聞くなという無言の圧力が彼女から垂れ流しにされていたのだ。だから聞くに聞けなかった。
「……戦争は集結しましたか? 閣下」
しばらくしたあと、モルヒネの麻酔で少しぼんやりしている司に夏葉は問い掛けた。閣下とはぐらかせたのは、プログラム中に司が名乗って目指していたあのアドルフ・ヒトラーにもじっているのだろう。そんな厭味にも似た大人の遊び心に特に嫌な顔ひとつもせずに、彼女は抑揚のない声で淡々と答えてみせる。
「プログラムは経過点でしかないわ……そうね、まだまだ戦争は続くの」
疲労困憊しすぎて頭がうまく回転しないのか、そっけなく答えた割には中身の薄いものだった。
「そうかいそうかい。それにしてもありゃぁ実に閣下らしい偉大な演説だったぜ?」
怪我の痛みはモルヒネにより緩和されていたとしても、精神的にも憔悴しきった状態で分校に帰ってきたものだから、一旦意識が回復した後、優勝者用にビデオを撮ると伝えたときにはどんな反応を見せるか内心ひやひやだったことを夏葉は思い出す。
『私の名前は蓮川司。高原市立高原第五中学校3年A組女子9番。千葉県高原市の少し奥側にある大地主の娘です。私が殺したクラスメートは15人。クラスの半分は私が殺しました。
待っててね、晴一君、貴正君、時哉君。もう少ししたら、帰ると思うから』
司の懇願によりその日の夕方に速報として放送されたその優勝者用にビデオだが、今日の朝もおそらく検死結果とともにもう一度流されていることだろう。この忌まわしきビデオを誰が見て誰が嘆いているのか、それは夏葉も青沼も知りえぬ範囲でしかなかった。
「……戦争はまだ続く」まだ第二次世界大戦は続きそうな兆候を見せていた。
「まだまだ途中ってわけか。……最後はずいぶんドンパチやったしな、別にプログラムだから違和感はねえけど……。ってかそれはその前がただ単に穏やか過ぎるっていう考え方もあるがな」
「……そうね」
「つれねーなー妙に不機嫌じゃないか。便所にでもこもるかァ? 何なら生理用品買ってきてやってもいいぜ?」
「……セクハラで訴えますけど」
「なぁ、何でそんな無愛想なわけ? 俺と会話するの嫌? まさか思春期?!」
「うざい」
おそらく疲れたのだろう。司はかなりぶっきらぼうに夏葉の質問に応えていった。
人間という生き物は危険が去ると副交感神経系の生理的要求が戻ってきて、ありえないほどの眠気を感じるときがあるらしいので、現在彼女が呆けているのもその一環かもしれない。それにしても司は国営病院に収容されたあとすぐに手術を受け、そのあと丸半日以上眠り続けていたのだから、そろそろその生理的欲求が満たされてもいい頃合なのだが。
「ひっでぇー、先生泣いちゃうぜ?」
元々人と接することを拒んでいた司の性格を知っている夏葉は、特に言うほど悲しむ様子は見せず、肩をすくめた。その代わりそわそわしているのは向かい側の座席に座っている青沼だった。
「ここ、うちの前ね」
その後しばらくして、少し細くなった市街地の道を通っているときだった。司が突然黒いシールが張ってある窓を開けて外を見た。城郭のような壁がかなり長く続いているのが見える。夏葉も歳に見合わず身体を乗り出すと、窓に手を掛けてその外にある光景を見つめた。どこぞのお城の城郭のような白い壁、そして紺色の瓦がその上に乗っている。――この中に、このアドルフ・ヒトラーと言う復讐者を生んだ元凶が眠っているというわけか。絶対零度の氷を作り出せるような冷凍庫が――
「あ?! お前んち、こんなでかいわけ?!」
「知らなかったの? 高原の蓮川といえば有名じゃない」
「残念でしたー! 俺は高原市民じゃありませんから!」
「……どうでもいいけど、もう少し大人らしくなったら? 三十路のクセして」
「ばっかやろう! 俺はまだ29なの! 花の二十代なんだからな!」
これじゃぁどちらが大人かわからないな、といわんばかりにため息をついたのは司だけではなく青沼もそうだ。ずいぶん昔に夏葉が大人は年を取るごとに子供心を思い出すと豪語していたのを思い起こした。
車が家の城壁を軽くスルーしてしまうのを見て、彼女は少し驚く。
「家に帰らなくていいの?」
「誰だよ、卒業式に出たいってほざいたの。卒業式は9時から始まるんだよ。お前はセンセーのありがたーいお話聞いてなかったのか!」
「あの時は先生が何も言わなかったけど? 今考えてみればプログラムに選ばれるからってこんなに連絡おろそかにしていたのね。自分の受け持つ生徒がどうせ死ぬって分かってたら、おろそかにしたくなる気持ちも分からなくはないけどさ」
「あーもう、ほんっと可愛くねーなー。屁理屈って言うんだぞそれ!」
「それより、担当教官が卒業式になんて顔出していいわけ?」
「ああ、その点はご心配なく。プログラムが終わった今、俺は担当教官の夏葉翔悟じゃなくて、担任クラスがプログラムに選ばれた不幸な担任の夏葉翔悟ですから。卒業式には最初ッから出てないとな。仮にもA組は卒業証書授与の最初だぜ? それに校長にも報告しなきゃな」
今後の方針をぺらぺら話す夏葉を見つめた。彼に「なんだよ、気持ち悪いな」と切り返されるまで黙り続ける。
「ずいぶん使い分けの演劇が得意なのね」
「……ハッ、お前には負けるよ」
頭をこつんと叩かれ、彼女は大げさに肩をすくめる。
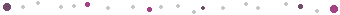
どうやら中学校が近づいてきたようだ。何年か通った通学路の通りに車が走っている。もう少し行くと学校を縁取るようにして植えられている桜の並木が見えるはずだ。以前ニュースで少し触れていた桜前線の話も、今は遠い昔に聞いたような気がしてきた。
「そーいやよ、お前」
頭の後ろで手を組んだ夏葉がぼやいた。それによって司の無言の物思いも中断する。
「普通の中学3年生なら持っててもおかしくない人命へのためらいが、お前にはかけらも見当たらなかった。んで? ……お前、何考えてるんだ?」
急に視線を鋭く変えた彼がそう聞いた。やはり政府の人間、それなりの鋭さがないと生きていけないのだろうか、と司は少し思いながら瞑っていた目を少し開ける。それから横を向いて問いかけた張本人を見た。悲しみに歪んだような微笑を浮かべて、彼女は答える。
「……正義を語れるだけの力が欲しい。私のしてきたことが、全部正義だと肯定できるくらいの力が」
辻褄がまったく合っていないが、それが問に対する答えなのだろうか。司はまた目を閉じてため息をついた。
「好きだった人間もその手で殺した、それをも正義だと認めたいとでも?」
そんな夏葉の問いかけに司はピクリと眉間にしわを寄せて能面のような表情を一瞬だけ崩した。
「私が、響を好きだったとでも?」
「間違ってるか? てーか。俺、新宮のことなんて言ってないけどなー。なんたってお前が殺したのは15人だぜ?」
墓穴を掘った。彼女は一瞬視界が真っ白になっていくのを感じた。司のしてきたこと、生きてきたすべてに興味があるのかわからないが、夏葉の質問はほとんど単刀直入で、デリカシーの欠片もないようなものばかりだった。もうこれ以上自分というテリトリー内に踏み入れてほしくないのに、夏葉は汚れた土足で遠慮無く入ってくる。
そんなよこしまな質問の所為で、彼女の脳裏に急に蘇ってきた新宮響の姿を見ることになった。どんなに撃たれても立ち上がり、もうこんなことはやめろと訴えかけようとしていたあの姿。少し哀れにも見えたその姿を思い出しては、胸がはちきれそうになるほど痛む。一拍置いて、どうして私がそんなことを思い出さなきゃいけないの?と思い出したものをすべてかき消した。
「少なくとも、ずっと優しくしてくれた男をその手で殺すのには少し躊躇いがあったみたいだな。お前、新宮のこと見ると逃げたし」
まるでその状況をすべて見ていた、といわんばかりに夏葉は平気でぺらぺらと話す。逆にこちらからどうしてそんなことを知っているの?と聞き返してやろうと思ったが、別にいいと思ったのであえてしなかった。――盗聴器が首輪に仕掛けられていることを、生徒は知らないのだ。
「響は……お母さんに似てた。お母さんが死んでからは、私のお母さんみたいになってくれた」
家庭での唯一の味方が死んだ中学2年の夏、それ以降途端に司の性格は豹変してしまった。ただでさえ口数が少なかったのに、余計に話さなくなった。その上灰色がかった髪の毛をベージュに染め、人から距離を置き、屋上で過ごす時間が多くなった。それらの原因となった父親殺害未遂の件、それから兄たちの母親他殺の件は、まだ小さな器でしかない司の心を破壊するには十分すぎたようだ。
壊れたガラスの破片のような司を、一つ一つ丁寧に拾い上げて付け合せてくれたのは紛れもなく新宮響。少年院行きを金で伏せられ、単に家族の事情で、と言う普通の嘘を真剣に飲み込んで、味方のいない彼女の味方になると言っていたことさえ懐かしい。
――私、響の事好きだったの?
少し自嘲気味に自問すると、彼女は自分自身の両手を見つめた。今は術後綺麗にされて普段の色白の肌を戻しているが、プログラム終了の時点では、それはそれは汚い色をしていた。その手で、響を殺した。引き金を引いた。『自分』を殺した。――汚い。響はあんなにも綺麗だったのに。
「……ねえ、先生は社会の先生だから、知ってるよね? ヒトラーは最愛の恋人エヴァ・ブラウンと死ぬ前に婚約して、あの世で結ばれたの」
汚い色がしみこんでいるその両手を凝視したまま、彼女はそうつぶやいた。
「私はヒトラーの生まれ変わり。だけどね、結末は違う。私に好きな人なんていない。例えば私が響のことを特別視していたとしても……私が堕ちる場所は、響の逝った場所と違うんだから。もう二度と会えない」
彼女は一切の涙を流さなかった。彼女の涙腺は枯れていた。頭の中から泣くという動詞をを消去した。それでもどこか、表情だけは悲しそうにゆがめていた。
「……悪い」
ぐいっと肩を引き寄せられて、頭が隣に少し間をあけて座っていたはずの夏葉の胸に押し付けられた。漸次、どうして彼が『悪い』と謝ったのか彼女には理解できなかった。どうして謝るの?私に謝ったって、損得は何もない。
答えは出なかった。その代わり少しタバコのにおいが染み付いた服がすぐそばにある。雨で冷え切った肩に、急に大きな存在が乗っかったような気がした。彼の大きな手が司の肩にまわる。
あったかい。
「忘れてたよ。お前が史上最強の不器用女だってこと」
たった1年間という短い期間の非常勤での担任だったが、それだけでクラスの生徒の性格を大体把握することは出来る。仮にも夏葉とはいえ一度は教員免許取得しようと粘っていた人間なのだから、人間をよく観察することについての能力に長けている。その台詞を聞いて司はようやくなぜ夏葉が謝ったのかを理解できた。
「ハッピーエンドで終わることだけが、この世のすべてじゃないっすよ?」
正面から微笑みかけてくる青沼が優しく言ってくれた。あまりフォローにもなっていないようだが、それは彼なりに試行錯誤して編み出した励ましの言葉らしい。
彼女は、夏葉のタバコ臭いパーカーをぎゅっと握った。
「お前が何しようかだなんて別にどうだっていいよ。……ちょっと興味あるけどな。だけど何をするにしろ、弱みはここに全部置いていけよ。プログラム優勝者は表面上は英雄だがな、所詮は殺人鬼だよ。特にお前みたいなのは、な。分かるか? お前に陰口無しの成功は望めないんだ。折れるくらいなら、ここで全部折っとけ。青沼の言うとおり、何も幸せになることが人生の全てじゃないんだからな」
幸せになることが人生じゃない
おそらく何も考えずに言った言葉なのだろうけれど、司にとっては大きな一言だった。小学校1年生より続けられた道徳の時間では、いつも成功する事や幸せになる事が、人生の目標だと説かれてきた。そしてそのうち、そうでなければ幸せじゃないと思い込んでいた。
――だけど……幸せって、何だっけ。
幸せを知らない弱者は、輝くような『幸福』を手にしようと奮闘するが、不幸しか知らない司は、常に不幸になることを選んだ。
「ねえ、先生。私ね、誓ったの」
「誓った? 何を、誰に」
「強くあれ、誇り高きものであれ。お母さんに誓った。だからね、先生。私はもう泣かない」
ハッピーエンドで終わることや、幸せになる事だけが、人生じゃない。
殺人に慣れた理性が、イエスと肯定した。
「でもね、最期の最期には笑って死ぬ事にしようと思う。腹の底から笑ってやるのよ。私の――復讐という名の存在理由をね」
Next / Back / Top
