動物のものと思えるような雄たけびが聞こえたのは、ドアが薄っぺらい所為ではないだろう。
血のにおいがかすかに隣の部屋からしてきたと思うのは、俺の鼻がおかしい所為ではないだろう。
だから……。
部屋のドアの前に人の気配がするのは、せめて勘違いから発生する思い違いだと信じていいだろう?
南京錠を6個つけた次兄の貴正の部屋のドアは、1日に2回しか開かれない。決まって朝9時に出される朝食と、夕方8時に出される夕食をとるときのみだ。それ以外はほとんどあかない。確かに4年前までは南京錠は1個しかなかった。年に一個ずつ、増えていった。それは貴正のささやかな恐怖心の表れだったのかもしれない。何だかんだ言いながら、血のつながった、しかも顔が似ている妹に殺されるとはずいぶん皮肉な話だ。それもこれも、全部自分が悪いと分かっているのだが、それで殺されるのは理不尽と考える俺ははたしてただの我が侭なのか?彼は悩んだ。
母親が死んでしまえばいいのに、そう考えて“あの計画”を持ち出したのは紛れもなく貴正だ。
当初、本当にあんな方法で母親が死ぬとは思わなかった。言い訳に聞こえるかもしれないが、あんな子供だましなことで母親が死ぬとは思わなかったのだ。持病の心臓病は薬を飲まなければだめになってしまうとよく耳にしていたが、本当にあれほどあっけなく死んでしまうとは。
棺の中で目を瞑る母親を目にして、その真っ白な肌に触れ、冷たさを感じた。嫌悪するほどの無表情なその顔に触れて、ようやく彼女が死んだと理解した。とんでもないことをやらかしてしまったと気付いたのは、葬式のあと兄弟三人で母親殺しの計画を話していて、運悪くそれを司に聞かれたとき。母親と瓜二つのその顔が、この世のものとは思えないものを見たかのように驚愕の色を示していたときだ。
罰を、受けるだけ。
母親を殺した、罰。
左手首に付けられたリストカットの痕。
誰も気付いてくれやしない孤独。
なあ、どこに逃げればいい?
何を憎めばいい?
タタタタタタタ……と小気味がよい音がしたのはそのときだ。ドアに付けられたはずの南京錠が、音を立てて吹っ飛んだ。驚きの吐息をつく暇もなく、次の音がした。
バタンッ!!
連続音のあと、鍵が外れたドアが思いっきり力強く開けられた。2階の部屋の中でも最も広く、それでいてどこか殺風景な部屋に、緑系統の色で施された作業服に真っ赤な血を彩った人間がずかずかと入り込んできた。
「南京錠なんてかけちゃって、ずいぶん引きこもりに拍車がかかったみたいね」
ベージュに染めたその長い髪の毛を後ろでひとつに縛っている“それ”は、手にマシンガンを握っていた。よく漫画などで見かける、あれだ。
「ああ、それね……。ジェイソンがチェーンソーじゃなくてマシンガン持って俺を殺しに来るのが、怖かったものだから」
ここ数年でずいぶんまともな言葉が発せられるようになった。昔は人との会話を極端に減らしていたためか、兄弟とでさえもほとんどまともな会話を続けることができなかった。――いや、そんなことはどうでもいい。目の前にやってきた異物を、川に水が流れているように当然のごとく受け入れている自分がいた。
「ずいぶん正直じゃない。そういうの、嫌いじゃないわ」
ニヤリ、と笑った。そいつは紛れもなく、妹の蓮川司だった。
4年も経ったからか、少し大人びた表情になっている。それでも、貴正は生まれて以来一度だって彼女のこんな粘着質な微笑を見たことはない。いつも無表情で何かを疎遠するような冷たい表情ばかりしているものだと思い続けていたのに。
――ああ、間違いなく俺は殺されるだろう。
仮面をはずしたジェイソンが真っ直ぐ見ていた。司が家族を殺す目的はただひとつ。それはこの家に住む人間なら誰だって分かっているだろうこの事実。
コイツは、母親のカタキを取りに来た。俺たち兄貴が母親を殺したのを知っていて、殺しに来た。
4年間ずっと怯えていた。いつ司に殺されるかわからない。明日には死ぬかもしれないという恐怖心を抱いて。
それでも4年間は長かった。この長い空白の間に、いつしか司はどこかで死んだのではないかとさえ思っていた。でなければプログラム終了後、すぐに殺しにこないことに納得がいかなかったからだ。もし本当に殺したいほど憎んでいるのなら、どうしてすぐに殺しに来ない?彼女に対する謎は深まってばかりだが、ひとつだけ揺るがない事実がある。そう、彼女は俺たちを殺そうとしている。俺たちを殺すために、司は今まで生きてきたのだ。これだけは、確かな事実だ。
「俺を殺すか」
天罰が降りる日が、まさに今日だ。この日が怖いなら、とっくのとうに自殺していた。それでもしなかったのは、もしかしたらもう来ないのではないかという明日への希望が少しあったからだ。電車が運休したとき、すぐに動くことを信じて待っていたが、結局は何時間も長く待たされるのと同じである。今か今かと思いつつ、結局何かが起こるまで待たされる。安っぽい希望をちらつかされる。
「隣の部屋で声がした。寝てる父さんを殺ったのか?」
「ふふっ……興味があったら行ってその目で確かめてくれば?」
やけに大胆不敵な行動をとり、その余裕ぶった表情と話し方が癪に障った。だけどあの絶叫と司にかかった返り血の量からして、壮絶な修羅場がそこにあると考えていいだろう。知らないことも、幸せのひとつだとさえ思った。
「ずいぶん冷静なのね。お父さんも晴一君も、あんなに取り乱してたのにどうして。逃げられないって、分かってたの?」
もうどこにも逃げられないことを盾にしてだんまりを決めているからか、司が不思議そうに聞き込んできた。
「俺は、わかってたんだよ。お前に“あの計画”を聞かれたときから、お前がこうやって俺たちに復讐しに来るって事くらい……わかってた。だから、ずっと覚悟してた」
手を握り締めて汗ばんで気持ち悪い感触を確かめる。生きている。まだ、生きていた。しかし逃げられない。いつ来るか分からなかった運命には抗えない。
「その割には厳重な警戒じゃない」
「正直、怖かったんだよ。死ぬことが」
そう、死ぬことは怖かった。殺されるとわかっていても、自ら安上がりな希望をかき消すことができなかった。すがり付いてでも、何とか生きようとした。そうやって死ぬそのときまで自分を正当化した。罰が下りなければ、自分たちの罪が赦されたと勘違いしていた。
「……それはずいぶん被害者的な立場にいるのね。冗談じゃない。貴正君たちは、立派な加害者。そうやって世間の同情被ろうったって、無理よ。そんなに覚悟があるなら、もちろん私がしようとしてることに耐えられるよね?」
ニヤリ、とまたあの粘着質的な笑みを浮かべた。司がやろうとしていることはひとつ。たった一つ。分かっていた、逃げてきた。
もうダメだって、分かってる――立ち上がって何も置かれていない机の前に立った。引き出しを開けて、それを取り出す。
「俺はずっと決めてたんだよ。お前が俺たちに復讐しようとするなら、俺はお前の復讐をその前に断絶してやるってな――」
手にしたそれ、出刃包丁を首に掲げた。手が、震えている。出刃包丁を手に取ったはいいが、指先に血が通わず手が震えていることが分かった。5月下旬、そろそろ大分暑くなったというのに、この寒気は何を意味しているのだろうか?
後ろを振り向くと、驚愕した表情でこちらを見つめる司がいる。
「ちょっ……!!」
そんな声が聞こえる一刹那前に、出刃包丁を一気に首に滑らせた。
グシュゥッ……と耳元で何かがはじけた音がした。生暖かいものが勢いよく飛び散り、手にしていたはずの包丁が床に転げ落ちた。白かったはずの壁が、一気に赤く染まっていく。
「何してんのよ!!」
司が近寄ってきた。頭を掴み、首に無理矢理押し付ける。傷を塞ごうとしているのか?
「勝手に死なないでよ! 冗談じゃないわ、アンタこそお母さんを殺した人間だって、私知ってるのよ! アンタには最悪な死に方用意してあげてたのに、先に死のうとするなんて勝手なことしないで!!」
罵倒された。
「嘘でしょ?! 死なないでよ、ねえ、まだ死なないで! これからね、一発ずつ銃弾打ち込んで、目でもえぐってやろうかと思ってたとこなのよ?! それからね、もう二度とあんな最悪なこと起こさないように口にナイフ付きたててね、その腐った頭をドロドロにかき回してやろうかって思ってたの! それなのに先に死ぬなんて卑怯よ! 晴一君だって死ななかった! 命乞いはしたけど私が満足するくらいの屈辱を与えてやった! なのにアンタはどうして!? どうしてそうやって死のうとするの?! まだ終わってない。私の復讐が終わる前に死んだりしないで!!」
視界にもやがかかった。耳が水のようなもので塞がれた感じがした。
これが俺の、選んだ道。お前に苦しまされるくらいなら、恐怖さえ感じていた自らの死を選ぶ。
どうだ、すごいだろ?
薄れた意識。景色は血の色。死んだ母親の面影が色濃く残る妹の顔が目の前にある。
「……ごめん、かあさん」
最期の最期で、そうつぶやいた。
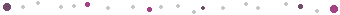
数十分してからようやく落ち着きを取り戻した司は、次兄の死体を前にしてぼんやりとしていた。貴正が母親殺害の計画の発端となったことは既に晴一の妻の夏樹から聞いていて、それならば兄弟の中でも一番残酷な殺し方で殺してやろうと考えていたのに、目の前でさっさとナイフで首を掻き切られ自殺されてしまった。死んだ後の人間の身体に拳銃を向けても、切りつけても、血は出ないし阿鼻叫喚を思わせる絶叫も一切彼の口から発せられることはなかった。それが悔しくてたまらない。目の前で死なれたのが悔しかった。
何もかも知った上で、貴正は司の目の前で死ぬことを覚悟し続けていた。愕然と恐怖のどん底に突き落としてやろうとしていたのに、彼はその一歩上からすべてを予測していたのだ。次兄の考えていたことをすべて想像すると、自分が兄に劣っていたと感づかされる。屈辱だった。
悩んでばかりもいられない。もう引き返すことができない道に立たされているのだ。そう考えて司の計画は一旦小休止をとった。
思えばここまで何とか軌道を外れず計画通りに事が進んでいる。
宅急便を偽ってこの家の人間に門を開けさせた。出て来たのは晴一の妻の夏樹。おそらくこういう機会を司が逃すまいと分かっていたのだろう。鉢合ったときに目が合い、彼女はニコリと笑った。そう、きっと彼女はもうすぐこの家の莫大な遺産が自分のものになると確信していたのだろう。遺産相続会議でどれだけの資産と土地を言い渡されたかは定かではないが、金に目がくらんで長男を落としたのも無駄骨ではなかったことがその笑みから見て取れた。
司はすっかり安心しきっている夏樹の背後から口元をクロロフォルムをしみこませたハンカチで覆った。程なくして夏樹の意識が途切れ、倒れこんだ。司は持っていたダンボールからロープを取り出すと、一旦夏樹の手足首を縛って、門から離れた場所に寝かせておいた。だから今、夏樹はこの家に入ってくる人間のだれの目も届かない場所で縛られたまま眠っているだろう。
それから家のドアを開け、すぐさまリビングを通って階段を駆け上がり、父親の部屋へと行く。このときにリビングにいた晴一にその姿を見られていた。本当のところは、あえて見せていたのだが。
テレビを見つつ寝転がり酒をたしなんでいた父親を殺害するのはいとも容易いことだった。そしてその場所に着た晴一を、苦しめて苦しめて苦しめて殺した。息子の泰も一緒に。
父親、長男、次男ときて、後は家にいないようだった。玄関に靴がなかったので、どこかに出かけているらしい。次に帰ってくるのが時哉だろうが真人だろうが洋介だろうが、すべての人間に与えられる等価的な罰は用意されていた。罪に対する等価的な罰――それはこの4年間考えあぐねた罰だった。
――お前なんか、死んじゃえば?
急に誰かの声がした。司は驚愕した様子で身を翻らせてあたりを警戒するが、それがただの気のせいだと察すると、また元に向きなおした。いつも聞きなれていた言葉――死ねよ――だからこそ脳裏にふっと出てきたのかもしれない。物心ついた頃から兄たちからは苛められ、馬鹿にされ、そして必ず一言「死ね」と言われる。父親からもそうだった。特に父親の修造は司のことを下等生物同様に扱っていたので、司が視界に入ることすら嫌っていた。
父さん殺そうとしたお前なんて、もはや『蓮川』じゃねーよ。
使えないんじゃなーい? オマエ。生きてる価値、ゼロ。
母さんも死んで、誰もお前の味方なんていくなったな。
次々と兄たちから浴びせられた罵詈雑言を思い出して、彼女はふっと微笑する。
ばっかじゃないの?死ぬのは、あんたたちなんだから。
彼女は次兄の部屋から出てまっすぐ行ったところにある2階の洗面所に向かった。水道のところにある大きな鏡に自分の姿を映し出し、ため息をつく。大量の返り血を浴びたその姿は、ほとんどが赤く染まっている。4年前、自分が優勝したプログラムでは『化け物』と言われ続け、それを拒んで否定し続けてきた自分がいた。無論今でもそれは否定できる。確かに次兄にはむざむざ目の前で自殺されてしまったが、それにしても兄と父は見事にうまく殺してのけたと自負した。そういうあたり、まだ『神』を名乗れる資格があると考えた。
かのアドルフ・ヒトラーも狂乱的な独裁者として後世に名を残している。多少狂っていなければ物事を推し進められない、そんな現状があったのかもしれない。ならば復讐という名の存在理由が終焉を迎えるまで、狂い続けるのみだ――司は心の中でうなずいた。
ヒトラーが最終的には狂ったことさえ美化して、司は久し振りにこんな言葉をつぶやく。
「私は、アドルフ・ヒトラー。ユダヤ人を抹殺するためにこの世に君臨した、神」
ぴかぴかに磨かれた白い大理石の洗面所。光を反射して司の顔をぼんやりと映し出した。
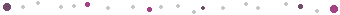
「たっだいまー!!」
小学校のころ、この家に住んでいたときと変わっていないセキュリティー暗証番号を入力し、大理石が敷き詰められた石畳をかけて、末っ子の洋介が帰ってきた。自転車で兄の時哉と真人と一緒に近くのディスカウントショップに出かけていたのだが、時哉も真人もそれぞれ買うものがあるらしく、暇になった洋介だけ先に帰ってきたのだ。彼にはどうやら見たいドラマがあったらしく、玄関のドアを開けるまでうきうきと心を弾ませていた。
「ただいまー! 泰ぁーあそぼー! テレビやるまであそぼー!」
自分の甥っ子に当たる泰は下に弟のいない洋介にとってみれば唯一の遊び相手だ。泰はまだ小さくて、中学3年生の洋介は可愛くて仕方がない甥との久々の再会に、嬉しくて1日ずっと一緒に遊んでいても飽きないほどだった。
「泰ー?」
ひょいとリビングを覗くが、泰らしき影がない。それどころか家にいるはずの長男晴一の姿も見つからない。どこかに出かけたのかな?と考えてみたが、家を出る前に見た晴一の二日酔いっぷりを見れば、彼が外出などできるはずがないとすぐにわかる。寝てるのかな?と考え、洋介はリビングより奥のほうにある階段のほうへと歩いていった。
「洋介」
「わっとおぃっ!! ビビッたぁー!!」
階段のところを上がろうとした瞬間に、聞きなれない声で呼ばれたものだからつい彼は叫んでしまった。次に「あれ……?」とこぼして階段のところに座り込む人影を凝視する。目をこすってみても、その影は消えなかった。
「え……司……姉、ちゃん?」
その影はまさしく、洋介が小学校4年生のときプログラムで優勝し、その後ぷっつりと音沙汰がなかった姉だった。
「久し振り」
司が目を細めて微笑むが、薄緑の作業服にたっぷりついたどす黒い血、顔に降りかかった返り血がそれらの優しい雰囲気をかき消した。過去の司よりも少し髪の毛は伸びて、それでいて同じベージュの色の髪の毛は後ろでひとつに結ばれている。その髪の毛にさえ真っ赤な返り血が降りかかっていた。どれだけ血を浴びたのだろうか、それは想像を絶する。そんな現実離れした姉を見て絶句した洋介は、数歩後ろにさがって壁に背中をぶつけた。
「な……なに、そ、れ……」
作業服の血を指差して、かろうじて搾り出した言葉で質問した。
「……これ? うん……お父さんや晴一君たちの血だよ……汚いよね。人殺しの血よ」
少し寂しそうな微笑に変わった瞬間、洋介は金縛りから解かれたように身体を動かした。はっと我に帰り、真っ白になっていた頭に、見えるものだけの情報を詰め込む。
「どうして……」
「分かってたはずよ。晴一君たちもこうなることを分かっていたはず。それでいて今日まで生きてきた。罪の意識背負って生きて、4年の間に少し幸せ見つけて、それからの転落という屈辱を味わせる。それが私の復讐。人生最大の苦痛を科すことがね」
階段に座ったまま司はにこりと微笑みつつそう語った。少し高い段に座っていて、目線は洋介よりも少し高い位置にある。陰陽のコントラストが司の表情を濃くしていった。その表情が変るたびに洋介はゾクリとする。いつの日か、プログラムに優勝したら絶対に自分たちを殺しに来ると苦言を呈していた兄たちの予言が、本当に当たる日が来たのだ。あの日はそんなはずがないと思っていた。ついさっきまでそう信じてきた。しかし洋介の信じたことは、すべて音を立てて崩れ去っていった。
だけど、本当に殺したのかよ?――彼は今だ目にしていない事実をいぶかしんだ。そうすることですべてが嘘に思えてきて、少し気が楽になる。そうだ、これは嘘だ。姉ちゃんの演技だよ、そうだそうに違いない!
「ごめんね、洋介」
ガチャリ、と静寂の中に違和感を覚えるような音がした。初めて聞き、初めて目にするそれは――拳銃の形をしていた。
「あ……お……俺……」
その黒洞々とした銃口を突きつけられ、再度金縛りがかかったように身体の神経が突っぱねて動けなくなる。非現実から現実を飛び越え、向こう側の非現実まで一瞬にして連れて行かされた気がした。
「俺を……ころ……すの?」
足がすくんで動けない。棒立ちのままかろうじて動く口だけを動かして問いかけた。その問いかけに少し寂しそうに笑って司は「ごめんね」と隠喩を用いた答えを返した。
「何で!!」
母親が死んだことが悲しかったのは、何も司だけではない。洋介だって三日間ほど泣いて学校に行かなかったこともあった。バスケットボールのクラブから帰ってきてみれば、母親の姿は既にそこになく、兄に連れて行かれた病院で母親の死を知った。クラブに行く前、笑顔で送り出してくれたはずの母親は、もう二度と玄関口に立つことがなかった。何の予兆も泣くあっさりと死んでいなくなってしまった母親に悲しんだのは司だけではないのに。それでも、洋介が兄から『俺たちが母さんを殺したんだ』と聞かされた時には司ほどの殺意は込み上げてこなかった。そこが母親を思う気持ちの格差なのかとは思ったが、やはり洋介にはいまいち理解できなかった。兄たちを殺すのならまだしも、どうして自分にまでその銃口を向けるのかという事を。
「……私の立場になって考えたことが一度でもあったら、きっと分かったと思う」
戦慄に押し付けられた頭で、この家の“普通”だった男尊女卑の風習を思い出した。司の立場――幼い頃はただ少し父親に嫌われている姉としか考えていなくて、どれだけの苦痛を姉が受けていたかを知らなかった末っ子は、思えば一度だって彼女の立場を考えたことがなかった。もし自分がそうやって、部屋の隅に追いやられて、自由さえも許されずに、家も正門から入れず、食事をするときはいつも他の兄弟とは別の時間にし、一番日の当たらない部屋に押し込められて、唯一の理解者だった母親を実兄に殺されたら……そうだったら、どうする?
何を憎む?どうしたい?どうしたらいい?何に怒りをぶつければいい?誰に助けを求めればいい?
孤独で、誰も信じられず、最悪な兄を持ち、馬鹿な弟を持ち、最低な父親を持ち、家を嫌い、世間を嫌い、自分を美化することも忘れて、ひたすら強いものに憧れた。
もし俺がその立場だったら――
銃口が、真っ直ぐ洋介の頭に向いていた。
「全部、壊したくなる」
パァンッ!!
洋介が言い終わるのが早いか、乾いた銃声の音が廊下と階段に響き渡るのが早いか。いずれにしろ撃たれた反動で壁に背をぶつけた洋介は、力無くして足から崩れていった。壁に叩き付けられた身体の背後には吹き出した血がまるで仏像の後光のように円をかたどっている。
パンッ!パンッ!
その後2発、司が持つCz75が火を噴いた。確実に狙いを定められた銃創は致命傷を貫き、身体を数センチほど上下に揺らしたと思うと洋介はすぐさま絶命した。
硝煙の立ち昇る銃口をいまだ洋介に向けたまま、司は微笑を崩さなかった。
「そう、正解。全部……何もかも壊したくなるわ」
不器用だから、一旦力を持ち始めると目の前のものを壊したくなる衝動に駆られて、すべてを壊し続けてきた。
力があったからこそ、司はその力をふんだんに惜しむことなく使った。
Next / Back / Top
