彼女の理想郷の完成までは、既に秒読みが始まっていた。
それでも“忌むべきユダヤ人”はまだ残っている。
武器はクルツサブマシンガン、そしてサバイバルナイフ、自動拳銃のCz75、セーフティの無いトカレフ、和室の床の間においてあった刀。
それから、何ものにも勝る鋭い、あからさまな殺意という名の
殺したい。殺したくて、たまらない。そんな情熱的な殺人への衝動。
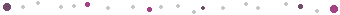
自転車を降りて門のセキュリティを解除した。四男の真人は5つ年上の三男・時哉と弟の洋介と共に昼食のあとディスカウントショップに出かけたが、久々という事でこの辺りがやけに懐かしくて、以前通っていた小学校や、制服を買ったっきり結局一度も通うことが無かった高原第五中などを回っていたら、大分時間が過ぎてしまった。安全のため、といわれて母方の親戚に預けられた洋介と真人はこの家にほとんど帰ってこれなかった。すべては司の復讐が怖いから、と何度も言われ諭された真人だが、この4年間はずっと疑問ばかり抱いていた。どうして自分たちを叔母の家に預けるなどして避けるのか。もし彼女のやりたいことが復讐ならば、どうしてすぐに来ないのか。この疑問は同等に洋介も持っていたようだが、末弟はそれ程気にしていなかったようだ。
そして昨日今日と父親の遺言を通告する会合が開かれ、そのために真人と洋介はおばに連れてこられてようやく4年ぶりにこの家に帰ってきた。ちなみにしばらく居候するつもりだったので、叔母は一旦家に帰らせた。
4年前までに父親が売り払った農地は埋め立てられて住宅街やマンションになっていた。農地は本来ならあまり住宅地向きではないのだが、そのあたりはうまく埋め立てたようだ。蓮川の家を取り囲む背の高い白い塀は相変わらずだが、どこか薄汚れているようにも見えた。そんな景色を見つめて、真人は家に入ってきた。大理石の石畳はチリひとつ落ちていない。几帳面な晴一の妻、同じく几帳面な夏樹の掃除の様子がうかがえる。
「ただいまー」
昔ながらの和風の扉を横にスライドさせると、ガラガラッという音がした。何気なく足を踏み入れ、かかとを踏んだ靴に手を掛けた。そのとき、
「おかえり」
と言う声がした。
ぞっとするほど冷たくて低く、それでいて水面上の波紋のような静けさを含んだ女性の声が真人の耳に届いた。身の毛がよだつ思いを一瞬で感じ振り向こうとしたその刹那、短く立てられた黒髪越しに固いものが頭に突きつけられたのを感じた。
「動かないで。動いたら撃つ」
真人は聞き覚えがあるその声を瞬時に記憶の中に残るすべての人間の声と重ねてみた。あれも違う、これも違う、試行錯誤の上に出てきた答えは2つ。母・美津子の声、それから姉・司の声。今思えば驚くほど2人の声は似ていた。
それから一発だけ、パァンッ!という音がエントランスの吹き抜けに響く。
――どうして、なんで?
反響してにわかにこだまする銃声を聞きながらそう思った。
口から吐息と共に零れ落ちた言葉の欠片。だが姉は突きつけた銃口が何も話さないように、何も言わなかった。心臓が張り裂けんばかりの銃声は後に彼の頭さえ打ち砕くだろう。はじめは突きつけられたものが正確には何か分からなかったが、先ほどの銃声で何もかもがはっきりした。頭のすぐ横で爆竹が破裂するような音がしたというのに、しかし身体は平素としていてそれほど動じなかった。極度の緊張感が身体の神経を馬鹿丁寧に一本ずつ引きちぎっているような幻覚に陥る。
殺される、そう思ったけれど真人は一度も振り向かなかった。これが兄たちが杞憂していた復讐、今起きていることが夢でないと確かめた上でそれを司の復讐という結論に結びつけると、彼は目を閉じた。
見慣れたはずの家が見えなくなった代わりに鼻腔を貫くような鉄の激臭とこれまたつんとする硝酸のようなにおいがする。彼は何かとそういった訳が分からないものに理屈を付けたがる性格をしていたが、さすがにこれらの異質なものたちに理屈をつけて理解するほど物好きではなかった。
「残念。せっかく会えたのにもうサヨナラしなきゃならないなんて」
背後で拳銃を突きつける司は、感情が欠片も篭っていない台詞を弟に浴びさせた。真人ももう16歳で高校2年生になる。この言葉の意味が解らないわけではなかった。
「……ねえ……ちゃん」
彼女を“姉ちゃん”と呼ぶのさえ4年ぶりだが、今の司はどうしても昔そうやって呼んでいた人間とイコールで結びつけることはできなかった。さあ、何が違う?真人は自問した。玄関扉のところに隠れていたのだろうか?背後から来たので姿は見ていない。声だって昔とさほど変わらないチャンネルだ。それでもどこか違った。これがクラスメート同士を殺し合わせるというプログラムを経て、復讐心の炎を焚き上げてきた姉の姿?昔のように、どこか冷たいのだけど弟2人には優しかった、あの姉の姿?
――4年の歳月が、姉ちゃんを何に仕立て上げたというんだ?
「姉ちゃん、俺、全部知ってるよ? ……姉ちゃんが、兄貴達……を、殺そうと……して、たことも」
春になって衣替えをし、日常は少し薄手のGパンに履き替えた。そのGパン越しに足が震えているのが見える。ああ、俺は怖いんだ、死ぬのが恐ろしいんだ――震えのあまりろれつがうまく回らなかった。
「俺だって、母さんが殺されたのは悔しいしビックリしてる! だけど……なあ、姉ちゃん。何がしたいの?」
4年間、叔母の家に預けられた中でずっと考え続けていた。姉の身になって考えてみた。殺したくなる気持ちも存分に理解できる。
だけどひとつ、たった一つだけ理解できなかったことがあった。
「どうして、すぐに殺しに来なかったんだよ?」
なぜ、4年も間をあけたのだろうか。
「真人」
答えを出されるのかと思い、反射で身体が硬直した。手も足もまるで金縛りがかかったようになってピクリとも動かない。
だが特にこれといった答えもつなげてこず、しばらく沈黙が訪れた。無声音の中、真人は自分が泣いているのにようやく気付く。命が惜しい?そうじゃない。理解できない悲しみがそこにある?そうかもしれない。こうなることは始めからわかっていた。晴一がそうしたように逃げも隠れもしなかった。だが生きることに未練はある。ただ姉の復讐なんて漠然としすぎて。訳がわからない。どうして、なぜ。こういうところにだけは、理屈を付けたがった。
「何……?」
振り向くこともできない。死の恐怖に屈し涙を流すそんな自分に、吐き気がした。そうかこの涙はまるでため息。無力なモノが吐き出した嘆息。
「背、おっきくなったね」
「……ああ」
「声、低くなったね」
「……そうかも」
「頭、いいんだってね」
「……どうだろ」
「ごめんね」
「…………ううん」
わかってた。
死ぬそのときまで生きるんだと、いつの日か次兄が唱えていたのを覚えている。そう、まさしくその通り。
ブラックホールを凝縮したような瞳に、疑問符を投げかけることは止そう。
きっと自分の死が何か姉に特があることなのだろう。
4年歳月を空けることも姉にとって有利になるのだ。
ただ、母親を殺した兄と同じ血が通っている人間として……自分が死ぬことによって彼女の黒くなった心をそっと抱くことができたら――
パンッ!!
司の握っていたトカレフが乾いた音をはじいて鉛弾を吐き出した。吐き出された鉛弾は迷わず直進し、真人の頭を貫通する。比較的破壊力の低いトカレフの銃弾は頭の中で運動エネルギーが急速にダウンし、大きな破壊を伴わず被弾者の前面部から飛び出した。それでも大量出血は免れることはできない。玄関のカーペットが朱に染まり、次第に黒くにじんでいった。銃声の余韻にかき消されて血が噴き出す音はそれ程大きくしなかったが、脳を撃たれたため硬直した身体がそのままの格好で玄関口のエントランスにどさりと倒れこんだ。
どくどくと湧き出る血の泉は止まることを知らず流れ続けていく。脳漿かと思えるような半透明のゼリー状の物質も同じように湧き出る。4年間で見違えるほど成長した真人の身体は、痙攣のため今もなお震えていた。
最後に1回、引き金を引く。同じ銃声がしたあと、真人はもう動かなくなった。
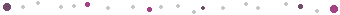
「うらうら野郎どもー! 時哉様のお帰りだぞー!」
両手に半透明のビニール袋を吊り下げて、その中にビールとつまみいっぱいにして帰ってきたのは三男・時哉。彼はディスカウントショップで弟達と別れたあと、適当の時間をつぶし、それから酒屋によってこれらの酒類を買い集めてきたのだ。帰ってくる前にどこかに寄ってきたのか、頬を赤らめ既に出来上がった状態で帰ってきた。相変わらずにへらにへらと笑いながらはっきりしない足取りで玄関扉を開けた。
「……あ?」
扉を開けた瞬間、仮想世界の中のようなものが目に入った。
両手に持っていたビニール袋を無意識に落としてしまった。缶ビールが派手な音を立てて袋から出て転がる。当たり前だろう、足元には広く巻き散らかされた血痕があり、目の前にいつも大きな花瓶があった場所に花瓶はなく、代わりに壁に「2階へ行け」と赤く大きな文字で書かれていたからだ。
「……んだよ……これ」
血の臭いがする。ただならぬ不穏な雰囲気に時哉は息をのんだ。
「書いてある通りよ。お父さんの寝室に行きなさい」
静寂を破るような異質な声。忘れかけていたその声にぎょっとして身体を翻して声のしたほうを振り向いた。その瞬間、パーンッと何かがはじけるような音がし、時哉は左肩を殴られたようにそこからバランスを崩した。
「ぎゃああああああああああああ!!!」
絶叫を轟かせて彼は倒れこんだ。一段上がったフローリング部分に血が流れ始める。時哉は痛みに耐え切れず撃たれた左肩を押さえ悶えて転がった。
「五月蝿い」
冷酷なまでにそうキッパリと言い放ったほうを向いて、彼は更に驚愕の色を濃くすることとなる。
「少しは黙ったら? 弱く見えるわ」
ニヤリと口の端を吊り上げ、黒い拳銃を右手に握るその姿は、この4年間ずっと畏れ続けてきた妹の司と同じものだった。
元々母親によく似ていたその顔も、歳月がたてば更に似てきて、一瞬本当に母親が行きかえってきたのかと錯覚したくらいだった。
「てめっ……司ァ!」ついにやってきたその復讐の象徴の姿を見て彼は奥歯を噛んだ。
いくら強がっていても内心は心の底から畏怖を感じていた。この復讐が恐ろしくて17のときに家を飛び出したのに、このザマは一体なんだ?!4年経っても音沙汰無いから忘れてしまっていたというのに、目の前に立つコイツは何者だ?!コイツはやっぱり俺たちに復讐しに来た。だったら俺は今まで、何のために生きてきたんだ?!
痛みのために潤ってきた涙でにじんだ視界の中に司の姿を捉えた。玄関の隙間から入ってくる光が逆行に輝き、彼女の色白の肌に刻まれている凹凸をはっきりと白黒のコントラストで彩る。薄気味悪いその嘲笑にゾクリとしたものを感じた。見下されている、完全に。光のない、まるで黒いガラス玉のような瞳と視線がかち合った瞬間に、瞳を覆う涙が凍てついたかと思い間違えるほど冷たいものを受け取った。
「動けないの?」
右肩の負傷によって全身からすべての力が抜けて、動けないことを知っていた上で司は足先で思いっきり銃創を残酷にも強い力で蹴りつけた。ぐっと詰まったような声を漏らし時哉は仰向けに転がってしまう。
「ってえな! ふざけんなよてめえ!」
痛みはするがとりあえず相手を罵倒するだけの体力と精神力はわずかに残っているらしい。年を重ねても変わらないその減らず口に張るためにガムテープでも持ってくれば良かった、と思っているかのように司は肩をすくめてうんざりした表情で兄を見下す。それから唐突に拳銃の引き金に指をかけた。その瞬間兄の目が大きく見開かれる。
パンッ……
司がまた引き金を引いた。銃弾は時哉の目の前の床に深く突き刺さり、その持て余すほどの運動エネルギーのために床は焼けて小さな煙を上げた。銃声が尾を引いて消えていく頃ようやく「黙れって言ってんだろ」と司が口を開いた。
「立てよ。絶望を見せてあげるから」
急に口調が変わった司。時哉は驚きによってもう一段階大きく目を見開き、その視界の中に鋭い目つきで睨みつける彼女の姿を見据えた。時哉のほうがゆうに15センチ以上背が高いというのにもかかわらず、彼女は時哉のパーカーの襟首を握り、引き上げて無理矢理立たせた。その力になす術もなく、時哉は抵抗もできずに引きずられ、長い廊下をずるずると這い、リビングの手前にある階段までつれてこられた。
「上がって。お父さんの部屋まで歩くのよ」
肩は撃たれたが足はまだ健在である。眉間に銃口を突きつけられ、本気で撃ちかねないと判断した時哉は、立ち上がって歩き始めた。司もその後ろをついていく。
屈辱が時哉を支配していた。今現在こうして歩くことも不名誉である。突きつけられた拳銃、これではどこかの囚人のようではないか?――今すぐにでも振り返って階段から突き落としてやりたかったが、まるで地獄の針山のように突き刺さる後ろからの視線がそれを拒んでいた。振り向けば、撃つ。そういう覚悟は彼女にある。別に司はいつ彼を殺したっていっこうに構わないと、彼自身分かっているはずだ。
そうすると困るのは時哉だ。どこに逃げたって、どう足掻いたって、残念ながら彼の行き着く先はたった一つ。死、あるのみというわけになる。お世辞にも頭が良いとは言えなかった彼は、なぜそうしてまでしきりに2階に行くように促しているのかまで考えは届かなかった。
「うっ」
2階にあがると閉めっきりのためか、春特有の生暖かい空気が充満し、それと共に何かが腐ったような不敗臭も漂ってきた。傷口を押さえて血で真っ赤になっている右手をとっさに口の前に持っていって初めて、そのにおいが何か理解する。血のにおい――彼の右手にべったり付いている血のにおいと同じだった。
「ほら、こっち。お父さんの部屋」
階段を上がって左手のほうに曲がると時哉の部屋も含めて男たちの部屋がそれぞれ割り振られている。一番奥が貴正の部屋で、その手前側が父親の部屋だ。吹き抜けのほうから入ってくる光がその廊下を照らす唯一の光源で、その光も日が傾いているために少し薄暗くなった。足元のフローリングを気をつけて歩いていくと、ふと違和感を感じるところにぶち当たった。父親の部屋の前、ざらつく感触があったのだ。
「……んだよこれ……」
足で削っていくと、白いスニーカーソックスが汚れた。
「ふふっ……あとで分かるわ」
耳元でボソリとつぶやかれた。仕草一つ一つすべてに蕁麻疹が出そうなほど過剰反応を起こす時哉は、精神的にも身体的にもそろそろ限界が訪れようとしていた。左肩からの出血は致命傷ではないが決して軽度のものではない。出血多量から引き起こされた貧血は徐々に視界から明瞭さを奪っていった。時々視界を横切る暗闇の向こうから誰かの手が伸びているのが見える。その手が手招きをしていた。冗談じゃない、誰がお前なんかに連れていかれるかってんだ。
がちゃり
ドアノブをひねり、父親の部屋の扉が開けられた。その瞬間時哉は後ろから突き飛ばされ、バランスを崩して畳の部屋に倒れこんでしまった。
「ってえ!」
肩を押さえていたためうまく受身の態勢を作ることができなかった時哉は痛みをそのまま受けてしまった。ここ最近取り替えたのだろうか、真新しい畳のにおいが香ったが、それ以上に香るものがあった。忘れられないもの、だけどいつから慣れてしまったのだろう、血のにおい。異臭のはずなのに、もう備考はこれらを普通と認識していた。いつからだろう。薬を取り替えただけの遠隔操作だけれども、母親を殺したあのときからか。そして年を経てその“普通”はもう一度ここに蘇ってきた。
「……嘘だろ」
うつぶせに倒れた上体から立ち上がろうと試みると、部屋の中の情景が否が応でも目に入ってしまった。時哉が覚えている限り、この部屋は10条畳部屋で、中央に父親の布団が敷いてある。そして部屋の隅には酒が入る小さな冷蔵庫があり、その反対側の角にはテレビが置いてあるのだ。ここで父親は一日中酒を煽り、気が向いたらパチンコに出かけ、溜めてあったAVを時々見てはその性欲を満たす。時哉から見ても、父親の、ましてや事業を取り仕切る人間の風上にも置けないような、最低な人間が棲んでいた部屋。
その部屋が今では、まるで使い終わって壊れてしまった等身大操り人形の置き場となったような物置と化しているではないか。
「ハハ……夢か、コレ」
具現化した“復讐”という名の戦慄をその目に焼き付けた。
父親が、両手を広げた状態で壁にはりつけにされていた。胸からは一本の刀が生えている。身体中血まみれだった。
長男が、仰向けの状態のまま両手をナイフで床に打ち付けられていた。切り傷と身体に開いた穴が見事に映えている。
甥が、首を切断された状態で父親である長兄の顔の横に置かれていた。胴体は見当違いの場所に転がっている。
次男が、首を妙な方向に向けて布団の上に倒れていた。頭がぱっくり割れていて、ドロドロとしたピンク色のものがこぼれていた。
四男と末弟が、2人揃って壁にもたれ、安らかに肩を並べていた。しかしその頭は2人とも見事なまでに打ち砕かれていたが。
「夢じゃない。コレが汚いユダヤ人の末路なのよ。大丈夫安心して。時哉君もコレにちゃんと追加してあげるから」
畳み掛けるようにぼそぼそと司がつぶやく。倒れたまま上半身をあげて呆然とその光景を見つめている時哉に、その声が少しだけ届く。「コレに追加してあげるから』という言葉だけがやけに鮮明に耳に入ってきた。目の前に展開されたグロテスクな蝋人形を見つめて、自分もこの中に入るのだと考えると、身の毛がよだつ思いをした。つまり、例外なくお前も私に殺されるのだ、という事を司は暗黙のうちに訴えているのだ。
「ユダヤ人……? どういう……こと……だ?!」
司がユダヤ人という比喩表現を使う理由など、時哉が知るはずもないしこれより先知ることもないだろう。司が”要らないもの”として例える表現であることは、彼の知る由ではない。
それでもなんとなく、時哉は司の言いたいことが理解できた。
復讐。
当時14歳といえどまだまだ幼くて、精神的にも一番不安定な時期に当たるそのときに、時哉たちは司から一番大切なものを奪った。
その報復。
気付いた時にはもう遅かった。
「こんな事しやがって……! てめえっ……何様のつもりだよ!!」
兄や弟、父の死体がそれぞれ司の憤怒が具現化されたように見えた。惨殺、否、もはや猟奇的殺人と言っても過言ではないほどの死体たちが物語っていたのは具現化された彼女の哀絶なのだろう。もちろん自分がしたことが悪いことだと時哉も理解している。しかし罰があまりにも重すぎた。自分がした罪が、これほど重かったなどまったく知らなかったのだ。だから当然のように時哉は口悪く司を批判する。それは自己防衛のため駄々をこねる子供と同じようなものだった。
「何様のつもり? ……ハハッ、決まってるじゃない」
彼女は目を細めてくしゃっと笑った。不器用なその笑みには寒気すら走る。あざ笑うかのように声を上げたあと、両手を広げて肩をすくめた。その姿は狭いステージ上で踊る道化師にも見えなくはない。
「神様のつもりよ」
パンッ!!パンッ!!
言い終わるのが早いか、司が引き金を引くのが早いか。とにかくニヤリと口元をゆがめた彼女が、うつぶせに倒れこんだままの状態で愕然としている時哉の背中、それから頭をめがけて引き金を絞った。まさに蝋人形のように、精密で、それでいてどこか現実離れしているこれらのコレクションのうちに、時哉も追加する作業をいそいそと始める。
子供がいくら遊んでもまったく満足しないように、司もいくら引き金を引いてもちっとも満足しなかった。明らかに絶命していると見えても、司はその手を止めなかった。父親の胸から生えている刀をおもむろに抜き、時哉の背中を数回切りつける。深く、深く、それは司の悲しみのように。
ようやっと満足したのか、司は時哉を切りつけていた刀をもう一度、父親のほうへと突き刺した。今度は何かを叫びたそうに大きく開けているその口腔に向けて刀の切っ先を突き立てる。生ぬるい感触を突き抜け、壁に突き当たった硬い感触がほとんど同時に訪れた。
彼女はもう一度ニヤリと笑い、返り血で汚れた口元をぺろりと舐めた。眼下に広がる血だらけの畳の上には、大嫌いだった兄たちと、弟達の死体がある。この部屋に、もはや普通はひとかけらも残されていなかった。しかしこの家にもとより普通などなかったのだから、何もかもが異常のままでよかった。
土足のまま上がった畳部屋。時哉の血の中に足を踏み入れると、ピシャッと小さな音がして緑色の作業服がまた汚れた。窓のほうへ寄っていくと、玄関や庭が一望できる一番いいところがある。そこに行き、一旦窓に腰掛けて振り向き、死体の数々を見た。時哉には死ぬという事を再確認してもらい、恐怖のうちのままに死んで欲しかったのでわざわざ死体をすべてこの部屋に運んだのだ。ご丁寧に、玄関のところには真人の血で2階に行けと書いて。
時哉君はどう思ったかな?――殺されることが嫌で、この家を一番はじめに逃げ出した三男坊は、死ぬ間際何を考えていたのだろうと司は思考をめぐらせた。
それにしても、こうして兄弟と父親を殺し終えてずいぶん気が楽になったように思える。それに恍惚感もプログラムのときとはまるで種類が違う。
ついに、ついに私はやったんだ……終わったんだ……ほとんどが。
野望の、しかしそれの約8割がここに終了した。残りの割りは第三者に任せ、彼女が出来ることはすべて終わったのだ。
部屋の出窓に手をついて外を眺める。ここから見ると門より少し離れた場所に寝かせてある晴一の嫁、夏樹の姿がよく見えた。遺産目当てで晴一に近づき、殺されるかもしれないという彼の恐怖心を表面優しく慰め、そのまま成り行きで一緒になってしまった女が。今頃彼女はどんな夢を見ているだろうか?損はさせないと約束して近づいてきた司が兄弟を殺し、蓮川家の莫大な財産をすべて自分の懐に入れた夢でも見ているのだろうか。しかし夏樹は知らない。彼女もまた司の手のひらの上で踊らされているという事を。
大丈夫、損はさせない。……得もなせないけどね……。
ひょいと出窓の台から飛び降りると、もう一度倒れている兄たちのほうへと近づいていった。晴一のほうへと近づき、甥の泰の生首をふすまのほうへと蹴りつけふすまを破いた。動かなくなった時哉の少し長いの髪の毛を引っ張り持ち上げ、多少軽くなった身体を乱暴に仰向けにさせた。ブチブチっと音がして茶色い髪の毛が抜けたが、痛みを感じるモノはどこにもいない。手を振り払ってまとわり付く髪の毛をとった。
こうやって司は蓮川家の人間の身体を痛めつけることによって、過去の自分を少しずつ清算していったのだ。
好きで女に生まれた訳じゃないのに、女だからという些細な理由で忌み嫌われていた自分。そんな家で育った所為か、周りの人間に馴染まない人間性が育った自分。家での顕然とした男尊女卑という名の差別を受けていた自分。友達がほとんど居らず、楽しみの欠片もなかった学校に馬鹿正直に通っていた自分。強きものにあこがれた弱かった自分。そんなくだらない人生を送っていた自分。プログラムでクラスメートを15人殺した自分。そして、アドルフ・ヒトラーを語っていた自分。限りなく神に近づいたと自負していた、自分。それらをすべて消し去っていった。
最後に、ドアを前にして一度振り向いた。もう一体ここに新たに追加させられることとなる蓮川夏樹という死体を“回収”しに行く前に、もう一度振り返ったのだ。誰もが大きく口をあけ、悶絶していた。誰の目にも、もう光など映っていなかった。昼間ながら、さながら夜闇の地獄を見ている気分に陥る。この地獄を作ったのは誰だ?自分に問いかけてみた。自分だ。返答が帰ってくる。
部屋を出て、階段のところにある洗面所の鏡に映った自分を見つめ、不意にポツリとつぶやいた。
「これで……よかったのよね」
自嘲とも慙愧とも取れるため息と共に。
Next / Back / Top
